難敵の登場!!
最近、ものすごく手こずっています。もうすぐ13歳になる姪っ子。彼女の勉強のお手伝いをしているのですけれど、これがなにせ手強い。彼女は今、中学1年生。昨年までは公立学校に通っていましたけれど、中学校から私立学校に移りました。
というのも、姪っ子はお勉強がなにせホントに好きじゃない。公立校よりも面倒見がいい私立校のほうが少しは勉強を見てくれるんじゃないかと甘い考えで、転校したのです。けれども、転校したそばからコロナ禍でカンボジアでは学校封鎖が続いています。それでもそこはさすがに私立校、連日リモート授業が続いていました。
しかしながら、どういうわけか我が家に居候している姪っ子の様子を見ていると、どうもそのリモート授業もサボリ気味なのです。でもそこは面倒見のいい私立校、彼女がちゃんとリモート授業に参加していないと、すぐに彼女の母親に電話がかかってきます。そして、結局、それは私の妻に伝わり、妻から姪っ子にお小言となります。で、そんな流れになんとなく私も巻き込まれて、姪っ子の算数を見ることになりました。
やってみると、小学校で習うべきことがやっぱりできない。分数や少数の計算はかなり怪しい。掛け算九九も、7の段、8の段、9の段が不確かでした。そんなところからじわじわと攻めていきまして、すこしずつ中学校の範囲にも手を広げつつあります。姪っ子の母語はもちろんカンボジア語(クメール語)。こちらが話す英語も、なんとなくなら伝わる(はず?)。計算などは書くことでもコミュニケーションできます。私もごくごく簡単なカンボジア語なら使える。そんな感じで教える方、教わる方、双方よたよたながらも、なんとか進めてきました。
そして7月末で学校年度が終了しました。8月9月は学校はほぼお休みで、リモート授業も止まりました。リモート授業がないと、勉強する習慣が身についていない彼女は、携帯電話で遊ぶばかり。それで、連日仕事で忙しい妻に変わって、英語も私が教えることになったのです。
まずは自分で勉強する姿勢を身につけてくれればいいや、ぐらいのつもりで渋々引き受けました。英文を読んで、わからない単語を調べて、訳を(カンボジア語)でつけて、一緒に英文を読む。それを数週間やってきました。ところが、何かがオカシイ。
で、ようやく気がつきました。彼女、英語もやっぱり基礎がまったくできていないのです。自分で英文を書くと、He have a pen. とか平気で書く。うん、意味は通じるよ。複数形と単数形の間違いも、三人称単数の動詞に s をつけるのも、たしかに英語に疎い側からすれば、どうでもいいじゃん、と言えないこともない。けれどさ、それ、習ったでしょう? 習ったのに間違うのはまずいなぁ。
で、やっぱりと言えばやっぱりなんですけれど、数字もoneからtenまではいいけれど、eleven, twelveになると鉛筆が止まります。ということで、結局英語も初歩からもう一度確認ということになりました。
で、英語となると数学よりもずっと「言葉」が必要です。カンボジア語が達者でない日本育ちの57歳と英語が達者でないプノンペン育ちの12歳の女の子。彼女は、はっきりいって、甘やかされて育ってきています。しかも無類の内弁慶、つまり恥ずかしがり屋。ふたりで顔を突き合わせて、こちらの質問に、彼女は黙り込む。言うことといえば、「オッチェッ(わかんない)」。
これまで偉そうに海外支援におけるコミュニケーションの重要さを語ってきた私です。それなりに場数も踏んできたつもりの私です。いかに相手の心を開くか、なんてことを考えてきた私です。日本語ができればなんとかなる。英語だって、はっきりいって下手な部類ですけれど、でもその分「伝えたいことがある」その中身で勝負してきた(つもりの)私です。
ところが、日本語も英語も使えない状況で、12歳の子どもとのコミュニケーションに四苦八苦している。勉強が大嫌いな姪っ子は、私との時間は常に仏頂面です。顔全部、身体全体から、「勉強したくない!」光線が発せられています。顔には出しませんけれど、その嫌々光線にかなり圧倒されている私なのです。
大苦戦。毎朝、「あぁ、今日は教えたくないなぁ、寝てたいなぁ」と思う。いやはや、なんとも情けないことなのであります。
ずるずると出口戦略ないままだったアフガニスタン支援
さて、ここまでが長い前置きでございました。
あぁ、そうだよ、タリバーンだな、と姪っ子に苦戦しながら思ったわけです。
アフガニスタンで再び政権を握ったタリバーン。2001年9月11日の米国多発テロ、あのニューヨークの2棟の貿易ビルに旅客機が突っ込み崩壊した事件をきっかけに始まった米国のアフガニスタン侵攻後、20年に及ぶ戦乱によってアフガンでは約5万人の民間人が犠牲となり、米国がアフガンに投じた軍事費は約92兆円にもおよぶそうです。それが、米軍の撤退が始まった途端、あれよあれよと言う間にタリバーンが再興し、おそらく誰も予想しなかったような速さでほぼアフガン全土が掌握されてしまった。米軍が支援し、最新武器も渡してきた政府軍は、ほとんどなんの役にも立たなかったわけです。
米国(と西側諸国)がアフガニスタンに建設しようとしてきた民主的な国家は、あっと言う間に瓦解してしまった。普通選挙の力ってなんだったの? もちろん、タリバーンの強権的な統治を嫌ってアフガニスタンから脱出しようとする人たちも大勢いるようです。けれども、タリバーンを認めている人たちがいるのも確かでしょう。もしアフガニスタンの大多数の人たちがタリバーンを嫌っていたら、こうまで早い再興はなかったでしょう。
西側諸国の支援によって、学校も多く開かれたし、特に女子教育は拡大した。けれど、それが多くの人たちに支えられるだけの力は持てなかった。おそらく、女性のなかにだってタリバーンを支える人たちはいる。きっと多くの人たちにとって「戦乱」が治まることが最重要なのだろうと想像します。米国が支援した政府は、賄賂などもひどかったという話もあります。タリバーンの清貧さを好ましく思う人たちもいるのでしょう。
はっきり言って、米国のアフガニスタン支援は、援助としては大失敗だったということ。民主的な価値観は、アフガニスタンには根付かなかった。根付かせることができなかった。
武力による統治をしながら、民主主義を根付かせることができなかったのは、きっと当然でもあるのでしょう。米軍統治で得をした人たちは多くはなかった。92兆円の恩恵を受けた人たちが、今、アフガンを逃げ出そうとしていると書いたら、辛辣すぎるでしょう。けれども、そういう面があるのも事実なんだと思います。
米軍をサポートしてきた人たちだけではなく、たとえば日本のODAをサポートしてきた人たちも、ある意味、国際援助で潤う受益者たちだったのです。そして、そういう受益者はアフガニスタン全体の中では、けして多数者ではなかった。彼らはけして「悪者」ではないでしょう。ましてや、彼らの家族が悪者であるわけがない。でも、米軍の援助は、アフガニスタンを分断してしまいました。
そもそも、米軍は、そして西側諸国は、日本は、どんなアフガニスタンへの援助にどんな出口戦略を持っていたというのでしょう。その点でも、あまりにも不用意な米軍の撤退だったように感じます。けれども、そのまま米軍が駐留していても、きっと支援はうまくいったわけでもないのでしょう。結局、米国は撤退するしかなかった。そうでなければ、戦費(援助費)だけが湯水のように流れ、きっとアフガニスタンの貧富の差をますます拡大するだけだったんではないでしょうか? そもそも民主主義を欲していたのは誰だったのか。
女性の教育は大事です。国民主権にしても、普通選挙にしても、それを啓蒙する時間は必要です。でも、アフガニスタンではどうだったのでしょう?アブサヤフへの報復のため、米国大統領ブッシュ(息子のほう)が始めたアフガン侵攻は、けして長期的な視野に立ったものではなかったのは確かです。そのままなし崩しに始まった、アフガニスタンの作り直し。やっぱり無理があったのだと思います。
アフガニスタンの混乱を嗤えない
それで思うのです。生徒中心教授法とか問題解決型授業とかの支援も、同じだと。アフガニスタンのケースほど華々しくは散りませんけれど、これまでどれだけの支援(資金)が生徒中心の授業や問題解決型授業の導入に注ぎ込まれてきたでしょうか(現在進行系で注ぎ込まれています)? そして、その成果はどれだけ上がっているのでしょうか? もちろんゼロではありません。そんなの当たり前です。でも、投資した費用に対してどれだけの成果が上がったかが問われるのが、今の国際支援です。果たして、投資に対する十分な見返りがあったと言えるのだろうか?
実際に、教育の質改善支援の末端に係わっていたものとしては、なかなか自信を持って胸を張って、十分な費用対効果がありましたと言い切れないものがあるのです。もちろん、少しずつ人材は育っている(はず)。でも、プロジェクトが終われば、その中身は気がつけば(海洋投棄されるフクシマ第一のトリチウムのように)大海の中に薄まっていく(?)のではないだろうか。残念ながら、日々の学校の授業に、それほど大きな変化は起こせていないのではないだろうか。
つまり、私は簡単には米軍の撤退とその後のアフガニスタンの混乱を嗤えない。
それだけ、海外支援って、とてもむずかしい。そして、21世紀の4分の1を経過しようとする今も、支援の方法は確立されていないのです。小さな事例では、多くの成功例もあるでしょう。けれども大きな支援となると、すべてのケースが特例です。あちらで成功したかに見えたものが、こちらで使えるとも限らない。
そして、私にとっての強敵、12歳の姪っ子が、支援の難しさを改めて思い出させてくれるのです。舐めるなよ、と彼女は私に伝えてくるのです。いい気になるなよ、と。
もちろん、個人でできることは限られている。そしてどんな支援でも、効果はすぐには現れず、ある程度の長期的な視野が必要になる。その過程で、支援する側も、支援される側も、さまざまな障害に出くわす。継続への努力を奮い出す元気がなくなるようなときもある。あとは、それでもやり続けるかどうか。もちろん、自分のやっていることを疑いながら。より良く変化させながら。支援する側にも、持続発展性が求められている。
姪っ子とアフガニスタンから、そんなことを改めて学んでいます。
明日の朝も、挫けずに起きて強敵と向き合うぞー! やはりまずは仏頂面を崩すところから考えなくちゃいけないよなぁ。さて、どうしたものかなぁ。





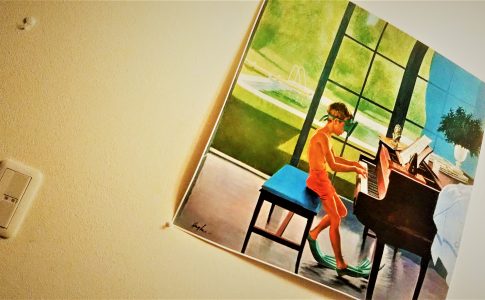








コメント、いただけたらとても嬉しいです