我儘(わがまま)少年? でも、とても楽しそうでいいじゃないですか
絵画シリーズ、連続3回め。今日は、ぼくの作業机の真ん前の壁にはってある絵です。実は、これを描いた人の名をぼくは知りません。たまたま絵画をあつかう米国のインターネットサイトで見つけて、とても気に入ってしまって購入したポスター画。その後、そのインターネットサイトは閉じてしまって、作者が確認できなくなってしまいました。知る人が見れば、あぁ、って思うのかしら。
(もし情報ありましたら、ご一報くださいませ)
で、この絵のどこが気に入ったか。水中メガネをかけて、フィンをつけて、上半身裸で、グランドピアノをひく少年。とても大きな窓の向こうには、よく整備された庭に水泳プールがある。どうやらお金持ちの家の、わがまま少年という感じもします。
でも、この少年が醸し出している、自由な雰囲気。ぼくはそれがとても好きなんです。
さらに言うと、そして実はそれが一番重要だったのですけれど、この少年、ぼくの子ども(今年、成人となりました)が幼いときと、ちょっと感じが似ているように思うのです。顔の形や体型や。そんなわけで、今、この絵がぼくの目の前にいつも(東京滞在中は)あるってことなんです。
そう、たしかに“自由”って、余裕がないとなかなかむずかしいのかもしれません。
「〇〇しちゃいけません」「〇〇は禁止します」そういう規制は、必要なときがあることはわかります。けれど、ダメ、というルールは、なんというのかなぁ、どこか心を萎えさせる感じがします。あれしちゃダメ、これしちゃダメ…、否定形のルールは少ないほうがいいなぁ。
肯定?のルールはどうでしょう?「〇〇してください」というルール。たとえば、「必ず〇〇を着用してください」、とか。これも、やはりときに窮屈に感じます。結局、ルール、規則は多くないほうがいい。
そんなぼくの苦手な「規制」を吹っ飛ばすような雰囲気がこの絵にはあって、そこがいいなぁと思っています。
ぼくには校則指導はできない!
一番いいのは、ルールなど特になく、それぞれ自分できちんと考えてわきまえて判断してやってね、ってこと。
「この広場ではキャッチボールは禁止です」と書いてある広場は、なんか自由じゃない。なんでキャッチボールをしちゃいけないのか?他の人にとって、危ない状況があるから。だから周りにだーれもいないなら、キャッチボールしたっていいじゃないですか。でも、周りに危ない状況があるならば、やめる。そんな広場が一番いいなぁ。
オーストラリア北部、ノーザンテリトリーにあるカカドゥ国立公園に遊びにいったときのこと(車イス者になる前)。公園内の滝や池でよく泳いで遊んだ(場所によってはワニがいますから、ガイドさんの同行なしで泳ぐのは危険です!)。身体いっぱい自然を体感するって、気持ちよかったなぁ。でも、日本の国立公園の滝で泳いだら、きっと怒られるんじゃないだろうか?何故だろう?
ぼくがケニアで理科教員をやって日本に帰ってきたとき、将来を考えた際、日本で教員をやるという選択肢はあった。けれども、ぼくには日本の学校のルールを自信を持って指導することはできそうになかった。
たとえば、制服を定めた校則。靴下の色、刺繍の有無、スカートの長さ…。あるいは髪型、髪の長さ…。
多くの国の学校で、たとえば女子生徒はよくピアスをつけて教室で学んでいる。小学生でも、中学生でも。でも、日本の多くの学校では、ピアスは禁止だろう。ネックレスや、イヤリング、指輪もだめだろう。
何故だろう?禁止の理由はどんな理屈だろう?
紛失したときの対応が大変?持てる子と持てない子の格差があることが表面化するのが問題?
でも、同じことはピアスの着用を気にしない社会の学校でも起こっているはずだよね。そんな学校では、貴金属を学校で紛失したら、どうするのだろう?犯人探しをするのか?それとも、それぞれの自己責任で済ますのか?(生徒の持ち込んだ持ち物の紛失に関しては、当校では責任を負いかねますこと、ご了承下さい、で済んでいるのかな)。
どちらかといえば、日本の学校のダメダメは、事なかれ主義にもぼくは思えるのだけれど。
服装チェックや、髪の長さをセンチメートルで計るとか、ぼくにはその必要性を自信を持って説明できない。あるいは、説明できるようになってしまう自分を想像するのも嫌だった。だから、日本で教員をするのは気が重たかった。結局、その道を選択できなかったというのが本音だった。
無駄なルールって、少なくないよね
たとえば、ぼくが若い頃から親しんだ野球にも、たくさんのルールがある。プレーにおけるルールはとにかく、プレーに直接関係のないユニフォームにも規制がある。色、ストッキングの着用等。
髪型に特に決まりはないけれど、坊主刈りが主流で、長髪だったら、それだけでなんか挑発的だ。ぼくが高校野球部の監督をやっていたときは「風で帽子が飛んでしまうような髪型はダメ」と選手に伝えていたけれど、それだって「何故、帽子が必要なんですか?」の回答にはなっていないですよね。打者走者がヘルメットをかぶらなければいけないことに関しては、硬球という固いボールを使うことの危険防止とはっきり説明できるけれど、守備の際に帽子、必要ですか?なくても、いいんじゃない?実際、外野守備など、プレー中に帽子が脱げてしまうことは少なくない。それで困ることは、特にない。
「オレは絶対、帽子をかぶって野球したくない!」という選手がいたら、ヘルメットはかぶれ!と説得できるけれど、守備中の帽子の必要性を説明するのはむずかしいだろう。でも、現状では、もし帽子をかぶらないで守ると主張しても、大会主催者側はそれを認めないだろう。それは、何故なんだろう? たとえば、旧英国圏で盛んなクリケットという野球によく似たスポーツでは、守備側は帽子をかぶっている選手もいれば、無帽の選手もいるんですよね。
無駄なルールは、どんどんなくしましょうよ。守備で帽子をかぶらない野球選手がいたって、いいじゃない?そんなのは、本質とは違うでしょう。守備で大事なのは、飛んできた打球にどう美しく対応するか、ってことに尽きるわけで。帽子なんか、どうだっていいじゃない(でもヘルメットはちゃんと被ってね)。
正々堂々、だから自由!
こんな記事を見つけた。
カーリング珍場面 ブラシが石接触、選手同士で解決|au Webポータルスポーツニュース (auone.jp)
記事によれば、2月14日に行われたカーリングの大会で、女子決勝で、勝敗に重要な場面でちょっとしたルール違反があり、そのルール違反をした選手による自己申告(それにより貴重な点数が取れなかった可能性大)により処理され、ゲームは進んだということだ。
ちょっと調べてみると、カーリングには審判はいるけれども、ゲームに関与することはほとんどないのだそうだ。ゲーム上のルールの適応は、選手同士の判断でなされることがほとんどで、たとえ自分に不利な状況でも、“スポーツマンシップ”の精神で正直誠実に対応することが望まれているし、選手もそうする、ということらしい。これ、素晴らしくないですか。
ぼくが野球をプレーしているとき。たとえば、ぼくが2塁手で1塁から盗塁してきた走者を捕手からの送球を受けてタッチしたとする。けれども、実は空タッチだった(実際にはタッチできていないという意味です、それをぼく自身は知っている)。けれど審判はアウトの判定をする。走者は悔しそうにベンチに帰る。こんなとき「いや、タッチできてないんです。だからセーフです」なんて自己申告することは、まず絶対にない。つまり、審判のミスジャッジがあっても、それが自分にとって有利な場合、自己申告でそれを覆すなんてことは、あり得なかった。
カーリングのスポーツマンシップと比べて、なんと小狡いことではないですか!野球というスポーツをやってきたものとして、カーリングに頭が下がる思いだ。
狡いことは、よくない。そして、そう考えて行動できたほうが、人は自由になれるんじゃないかな。伸び伸び生きられるんじゃないかな。
最近、プロ野球でもビデオ判定が導入されている。あのとき、ビデオを確認するのは審判だけだ。あれ、プレーに関わった選手自身が確認するってのはどうだろう?ホームのクロスプレーで、きわどいケース、あれは走者はセーフだと思うし、キャッチャーはアウトだと思うし、それはその場では解決できない。だから、両者がビデオ判定を確認する。それで、「あぁ、やっぱりセーフですね」みたいに両者が決める。ビデオを見ても両者が納得できない場合だけ、審判が介入する。そっちのほうが、“スポーツマンシップ”に則っているんじゃないかしらね。
自由と、教育と
長々と書いているけれど、つまりね、自由とルールとは、どうしたって関連しちゃう。ルールをできるだけ少なくしようとすれば、自己判断力は欠かせない。この自分たちで解決していく力をどう身につけるかが、教育のとても大事な役割なんじゃないだろうか。ルールで縛るのではなく、自分たちで納得いく方法を見つける。それが自由な心を育むことにつながると、ぼくは思ってる。
でも、そこでは、油断していると、空気を読む力ばかりを重視することになりかねないから、気をつけたい。大事なのは「昨日のルールと、今日のルールは変わってもいい」ってことだと思う(スポーツはそれじゃ困ることもあるわけですが、社会の中では、そんなことはあっていいと思うのです)。大事なのは、ルールそのものではなくて、それを決めるプロセス、さらには当事者たちの納得なんだと思うのです。納得のないルールは、自由を殺します。心を殺します。人は、肉体のみにあらず。自由な精神が「死ぬ」というのは、とても辛い。精神が殺されるって、ある。それは肉体を殺すのとまったく同じく、許されちゃいけないって思う。
昨今、忖度という言葉が飛び交っています。心遣いは必要だよ。配慮するってのも必要だよ。大事なこと。でも、昨今使われている忖度には、「心を殺す」という行為や判断が多く含まれているように思います。それは、嫌だ。そういう“忖度”は、やめて欲しい。
ぼくが高校野球選手だったとき。ぼくが所属していたチームにも“シゴキ”という名のもとの、「心を殺す」ことにつながる行為がありました。そして、それを見ながら、ニヤニヤしている“忖度”がありました。あれは、ダメだ。最低!あれも自由に反した行為でした。スポーツ界ほど実はスポーツマンシップという言葉が似合わない場所は他にない、なんてことが実際には多いように思うのです。そして、日本の学校教育にも、その残滓がちらちらと見えるのです。「決まりだから」と、心を殺す行為です。ミスを探す、減点法の教育です。
自由と越境も、関係しています。目の前に「線」がある。この「線」を跨いじゃいけないと言われる。どうして跨いじゃいけないの?と尋ねても、なかなか納得のいく答えがない。国境だから?決まりだから? そして、自由な精神を持った誰かが跨ぐ。反逆者が、跨ぐ。
日本の学校教育よ、世界の学校教育よ、反逆者を育ててみましょうよ。我儘少年少女の自由の芽を、どうぞ摘まないで。













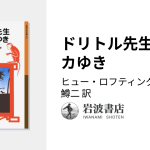
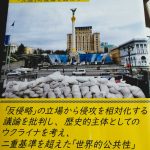

私が昔集めてたノーマンロックウェルの絵に似てるなぁと思って、ちょっと探してみたのですが、そのノーマンロックウェルとも交流があったらしきGeorge Hugheさんの絵かなという気がします。https://americanillustration.org/project/george-hughes/
ポスターはこちらに↓
https://www.art.com/gallery/id–a25677/george-hughes-posters.htm
rie様
George Hughe!!!!!WOW!!!
いやぁ、ズッポシじゃないですか! ありがとう、嬉しいです。(某有名インターネット書店での書評もありがとう、すっごく感激していて、でもそういえばお礼つたえてなかったですよね。ゴメンナサイ。もう、嬉しくて、舞い上がりましたよ)
George Hugheさんの絵、他にもステキなのがありますね。Norman Rockwell さんの絵も、夢があっていいです。集めていたって、この鏡に向かう少女、60万円以上もするよ!お宝。でも、一生で一回ぐらい、どーんと好きな絵、購入したらかなりハッピーかなぁ。
とにかく、教えてくださってありがとうございます。
村山哲也