当事者とは?
「当事者の話を聞く」という言い回しがあります。ある事柄が存在するとして、その事柄に直接関係している人が当事者。当事者ではない人は、第三者、傍観者、他者、というような言葉で表すことになるでしょう。
例えば、私は脊髄損傷(胸椎6番)による下半身完全麻痺の車イス者です。障害者手帳の区分けならば、「身体障害者等級表による級別」で下肢1級です。そして、つまり私は障害者当事者ということになります。
けれども障害者というのも実はとっても大きな括りです。障害者手帳の区別でいえば、身体障害の他にも知的障害(療育手帳)と精神障害があります。身体障害といっても、私のような下肢の障害以外にも視聴覚障害、上肢の障害等があり、同じ下肢の障害にも1級(重度の障害)、2級(中度の障害)、3~6級(軽度の障害)がある。
しかも、これらはあくまで行政による区分けであって、障害手帳を持たないけれど障害を持っているというケースだってあるはず。
このように多様な「障害者」であるのですけれど、ある機会に「障害」について何かが語られたとき、私が「障害者当事者」という枕詞を使って語り始めれば、非障害者である人たちは第三者的立場に退く気分になってしまうことが多いだろうと想像します。たとえそれが私自身の障害に直接に関係ない障害、例えば視覚障害、の話だとしても。
けれども、そこに視覚障害者がおられたとして、私は彼女/彼から「視覚障害の当事者でない人は黙ってて」なんて言われてしまう可能性もあるわけです。かように当事者という言葉は、なかなかその範囲について判断しずらい言葉でもある。
はたして、私たちは「当時者」という言葉をどれだけ信用していいのだろうか。実はけっこう疑ってかかってもよいのではないのかもしれません。
当事者とは立候補の問題。さらに、当事者という言葉が生み出す境界。
当事者というのは、自らがその問題の主体者である、という自意識の問題でもある。例えば私の介護者が障害問題を語るとして、「私は障害当事者ではないけれど、障害者の介護当事者として思うところをいわせてもらえば……」なんて枕詞が可能になります。これは私なりに通訳すれば、障害問題に対して主体的にかかわってきた者として、という風になるのだろうと思います。つまり当事者という言葉を本人が使えば、それはその問題の関係者であるのだと立候補するということなんでしょう。
その立候補に対して、上記の例であれば、「いや、介護者の話は後回しにして、障害者当事者の意見を聞きましょう」なんてせっかくの立候補を保留されてしまうなんて事態も起こらないとは限らない。もちろん、再度それに異議申し立てをすることだって可能で……。つまり当事者というのは、立候補しそれを認められるか認められないかというなかなかスリリングな状況を生み出すこともあるのです。私個人の嗜好としては、立候補のその心意気はできるだけ汲みたいなぁという気分はとても強いです。介護者であろうと、障害者であろうと、どちらも障害問題の当事者でいいじゃないかと。
当事者という言葉が出てくれば、そこには「当事者でない人は、黙ってて」という声が常に潜む。それを知っているから、多くの人は「触らぬ神に祟りなし」と沈黙を選ぶ、なんてことも起こっているのだろうと想像するのです。
このように。
往々にして「当事者」という言葉を自ら使う人に対して異議申し立てをするのはなかなかエネルギーが必要です。つまり、当事者というのはかなり強い言葉/立場です。当事者と当事者以外(第三者、傍観者、他人……)のあいだに明確な境界線を生みだす。当事者は特権階級を作り出す魔法の言葉でもあるわけです。もちろん、その特権が使えるのはその場限りだとしても、です。
“当事者”の怪しさ? 危うさ?
思い返してみると、私は若いころから、「立場」ということが気になっていたように思い出します。
たとえば、中学校のころ、クラスメイトが韓国朝鮮の人たちのことを悪く語っていた際に、「どうして彼は僕が韓国朝鮮の人ではないと判断しているのだろう? あるいは彼自身が自分を韓国朝鮮の人でないと判断している理由はなぜだろう?」と、不思議でしょうがなかった。
小学校中学年のころ、杉並区清水町の小さな木造一軒家社宅の4畳半の茶の間に流れた被差別部落民に関するニュースについて言葉少なに話す父母の会話を聞きながら、なぜ自分たちが被差別部落民とは違う存在だと言い切れるのか、やはり不思議でした。
だって、自分の祖先のことなんか全然知らないじゃないですか。今だって私は祖父母のことまでしか知らない。あるいは、家系図があるとしたって、どうしてそれが間違いないものだと言い切れるのか? 世の中には禁断の愛もあるだろうし、人には言えないさまざまな事情ってものもあったりするわけで。つまり、出自や血なんてかなり怪しいことなのではないかと、かなり幼いころから感じていた節があるのです。
そんな気持ちは、今流行っている「日本人ファースト」という言い回しを読み聞きするときにも湧き上がってくるのです。なぜ自分が“日本人”だと断定できるのだろうか、って。そこに疑いの余地を持っている人、あまりに少ないようで、それが私を驚かせ不安に感じさせるのです。
以前、このブログでも書いたように、私にとって“日本人”とはたまたまパスポート(これがないと国境を越えにくくて仕方がない)での所属ということに過ぎないのです。日本語人ということであれば、より積極的に肯定できるのだけれど。でも、日本人ファーストという価値観にはパスポート所有に限らないあれこれの付加価値があるようで。それを無条件?無根拠?に自分のものと納得できることが、私にはどうもよくわからない(ちなみにここでの日本人ファーストには、参政党のキャッチフレーズに限らずのそのような価値観のつもりでつかっています)。ちなみに、日本語人=日本人では、ないと思うよ。
あるいは、当事者をめぐって次のような話はどうでしょう。
ある漁村に原子力発電所の建設計画が持ち上がる。その交渉の当事者は、電力会社とその村の村議会なのか? もちろん村の住民ひとりひとりも当事者であるだろう。さらに漁業権を巡っては漁業組合がある。そこでも漁師ひとりひとりという立場もある。
その村にはきれいな浜があって、村民以外の人たちにも親しまれているとする。浜の四季を楽しんでいた村民以外の人たちはどうでしょう。通常彼らは当事者とは認められない。でも、どうして?
やがて、村議会が原発建設に賛成し、電力会社から支払われる補償金に漁業組合も同意し、建設反対当事者もいなくなり、原発が建設され完成する。浜は埋め立てられ、喪失する。
当事者の埒外に置かれていた 浜の四季を楽しんでいた無名の人たちは、完成された立派な原発を眺めて溜息をつくしかない。
こういうことって多々ある。当事者同士だけが決めたことが、けれどその当事者同士以外にも当然影響を与える。その浜はここでいう当事者だけのものだったの? 浜の四季を楽しんでいた人たちは、当事者ではないの? 「法律的には……」という説明はいくらでも可能でしょう。実際、その法律で当事者は決められる。当事者以外は、口出しはできない。
それならば、ある国立公園の森林伐採の問題は?国立公園は市民みんなの財産ではないの? けれどもここでも当事者と非当事者が存在する。その国立公園をハイカーとして楽しんでいた人たちほとんどは当事者としてその問題に直接口出しすることはかなわなかったりする。
たとえば辺野古は? 辺野古の海を埋め立てられるそのことの私は当事者なのか、当事者ではないのか?
たとえばガザでのイスラエル軍の虐殺は? 当事者は誰なの? ガザ住民とイスラエル軍? イスラエル市民は当事者? 米国在住のユダヤ人は当事者になれるの? 日本国籍で無宗教者の私は、当事者ではない? 第三者?傍観者?他人?無関係者?
当事者という言葉の暴力性ってあるよね。そう思いません?? 排除の理論。
私は、当事者って言葉の暴力性を感じることあるんですよ。お前は黙ってろ、と言われるかのような圧力を感じることがあるよ。
当事者の語りを大切に、という気持ちも強くあります。
「当事者の話を聞こう」という例文がすでに暗示するように、当事者とは少数者であり、弱者である人たちを指すのによく用いられます。その点で、社会的少数者/弱者の権利への(多数者/強者からの)注目/配慮が高まってきたことで、その使用頻度が増えてきている言葉でもある。もちろんその背景には、少数者/弱者側が、まさに当事者が、声をあげ続けてきたことがあるはずです。たとえばヘテロセクシャル(性的嗜好が異性に向く人)やシスジェンダー(誕生した時に割り当てられた性別と自己同一性が一致する人)でない人々を指す総称として立ち上がってきたクィアな人たち、あるいは障害者、移民といった少数者/弱者が「当事者」として社会的に確認されてきたわけで、その点では当事者という言葉を大切にしたいという気持ちが私にはあります。
一方ここまで書いてきたように、当事者という言葉によって生まれる新たな境界線の存在も気になります。それはけっして常に“立ち入り禁止線”ではないけれど、やっぱり多くの場合“立ち入り注意線”で“関係者以外は立ち入り御免”な気分を強く漂わすわけなのです。
けれども、当事者という言葉は、先に書いたように「主体性」と密接に関係しています。「私は当事者である」という立候補の権利について、それこそ他者があれこれ言うのは気をつけなくちゃいけないんじゃないだろうか。 そんなふうで、いつも私の心は揺れるんですよね。
さらにやっかいなのは、当事者を語る詐欺者の存在です。当事者という言葉が持つ暴力性は、詐欺者にはとても扱いやすいものだったりする。詐欺者は他者には黙っててもらいたいことが多いわけで、そこに詐欺者が当事者という言葉を使うメリットがあるだろうと想像する。
あるいは、例え当事者だとしても、他者の口をふさぐという意図で使われる当事者という言葉だとすれば、それは「少数者・弱者の声を響かせる」ことに寄与する当事者という言葉の役割からは遠いものでしょう。それは単にその場に小さな権力を生み出すだけだけだ。
そんなこんなで、「どうやって当事者性から生まれてしまう境界を乗り越えればいいのかなぁ」なんて私は悩んでいるのです。そんなときに、読んだのが以下なのです。
「背後に立つ」という越境戦略は、使える!と思う。
ここに紹介するのは、『残余の声を聴く 沖縄・韓国・パレスチナ』という本の中で、著者のひとり趙慶喜が担当の韓国の部分を書いた文章からの抜粋です。
「「背後」のない証言は無い」。そう述べた文学評論家の李知垠の言葉を参照しよう。
…証言はそれを取り巻くものと関係を結ぶしかない。であるならば、「背後」という陰険な言葉を再専有し、証言者の側から打ち立てることはできないだろうか。
振り返ってみると、すべての証言には「裏に隠れた背後」の聴取者がいる。…金学順ハルモニの証言が「最初の公式証言」であると記憶されるには、金学順ハルモニが日本政府を対象に戦争犯罪の責任を問うたからでもあるが、他方では、そうした「語りの場」を準備しハルモニの言葉を傾聴した「頼もしい背後」がいたからであった。…証言があるまで当事者ではなかった人々、戦争犯罪に反対した人々の努力が、またに金学順ハルモニの証言の「背後」である。そうであれば、私たちは「証言の背後に誰がいるのか」を問う代わりに「どのような背後となるか」を問うべきではないだろうか。
「背後」にある陰謀を暴こうとする旧世代の男性主義的な視線に対して、「背後」を自らの言葉で定義し直し、「背後になる」ことによって被害者と証言に寄り添おうとする人々がいる。「証言の背後になる」ということは、自ら被害者の声を聴き取り、証言をバックアップすることで問題の当事者になることである。被害者と支援者、証言者と聴取者といった相互関係を一対一の平面的なものではなく、相互に支え合う立体的な経験として捉え直すということである。(後略)(196~197ページ 『残余の声を聴く 沖縄・韓国・パレスチナ』早尾貴紀・呉世宗・趙慶喜/著 明石書店 2021)
上記の抜き書きの真ん中の段落は、韓国の文学評論家の李知垠の書いたものを趙が抜き出して和訳した部分となる。文中の金学順ハルモニ(1924~1997)は、1991(平成3)年に韓国で初めて従軍慰安婦として経験を自ら語った女性です。
ここで私がキャッチできた重要な点は、「当事者の背後となることで、自らも当事者になることが可能なのだ」ということです。もちろん、そこでは「誰の背後に立つのか」、そして「どのように背後に立つのか」が問われることになる。けれども、当事者の前で、第三者、傍観者、他者として立ちすくむときに、この「背後に立つ」という戦略はそこにある境界線を越えていくかなり有効な戦略だろうと、自分の体験に照らし合わせても、強く感じるのです。
思えば、「背後に立つ」という戦略を、私はこれまで知らず知らずに取ってきた。海外協力支援者として支援国の仕事仲間とかかわるとき、辺野古やガザやの情報に触れるとき、ポルポト政権の殺戮を語るカンボジアの友人の話に耳を澄ませたとき、私は背後に立つことで自らの当事者性を確保しようとしてきたのではなかったか。
「誰の背後に立つのか」は、どうしたって弱者・少数者の背後に立ちたいと思う。あとは「どのように背後に立つのか」という作法・技術を研ぎ澄ませばいい。この作法・技術は、本当に人それぞれで、自分なりの方法を見つけていくしかないのだろうとも思う。それこそが、年齢を重ね、経験を積み、知識を得る目的ではないのか?
実は人生において「当事者」としてものごとの先頭に立つ機会はそうそうは巡ってこないのです。それはそれで大変よろしいと思う。だって当事者として先頭に立つのは、きっとかなりエネルギーが必要なおっくうなことに違いないから。だからこそ、せめて静かにこっそりとでも「背後に立つ」っていう戦略、その心意気さえあれば、だれにでも使える機会が多いのだろうと思うのです。。
たとえば、ポルポト政権時代の監獄跡を訪問した後に私が感じた「カンボジアのことはカンボジア人の問題なのか」という問いを乗り越えて行ったとき、きっと私は「背後に立つ」という戦略を活用したのだと今振り返って思うのです。
だからさ、あなたも使ってみて欲しいよ、「背後に立つ」という戦略を。そしてあなたなりの方法を見つけ、それを磨いてほしいよ。ただ、やっぱり「強い者」の背後にはあんまり立つ必要はないと思うんだよね。立つなら、弱い者の背後のほうが、立ち甲斐があるってもんじゃないのかなぁ。






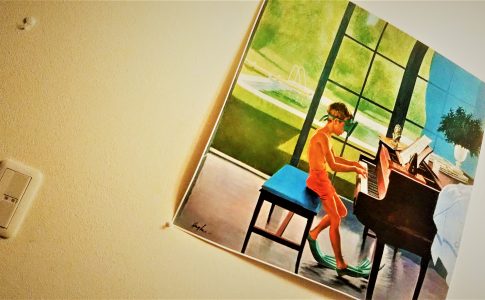







『当事者の背後となることで、自らも当事者になることが可能なのだ。』という意識を持って生きることの重さを想うとなかなか難しいことであるが被害者と支援者、証言者と聴取者といった相互関係を1対1の平面的なものでなく相互の支え合う立体的な経験として捉えれば、生きて来た時間や空間の中でその戦略は見出せるということだろうか。いずれにしても、その人の日頃の問題意識、自らをその問題の空間に投げ入れて人間としてのプライドに相応しい視座、立ち位置、座標軸をどう取るかにかかっているように思います。
匿名様、読んでいただき、コメントもしていただき、ありがとうございます。うれしいです。
はい、誰の背後となるか、それは自分自身の生きざまともかかわってきますよね、どうしたって。自分自身の座標、原点、それはきっちりと固定されていなくてもよいのだ、とも思います。揺れてしまう、あるいは相反する意見を自分の中で抱えてしまう、ということもあって当然。最終的には、縁(えん)、なのかなぁ。
社会問題における社会人としての立場を考える時、「当事者」という言葉をこのように深く掘り下げてみる試みは、かなり斬新で文章から気づかされる事がたくさんありました。このように丁寧に考えて行く事は価値のある事だと思います。
たか様。読んでいただき、コメントまで書いていただき、ありがとうございます。コメント嬉しく読みました。
斬新だったとしたら、書いて良かったなぁと感じます。ていねいに考えたい、でもどうしたって日々の雑事に追われてしまう、そういうこともあります。
それでも考え続けられたら、素敵ですよね。