『ガザ日記 ジェノサイドの記録』アーティフ・アブー・サイフ著 中野真紀子訳 地平社 2024
すでに14カ月続く虐殺の、最初の3ヶ月の記録『ガザ日記』
ガザの人々にとって戦争は天候のようなもので、私たちはずっとその中に生きている。私たちに発言権はなく、生まれたその日から、戦争はただ、やってきては去っていく。ほとんどのガザ人はこの地区の外に出たことがない。戦争が当たり前でない生活がどのようなものか知らないし、自由が何かも知らない。それを欲していることは分っているが、実際に味わったことなどないのだ。(『ガザ日記』274ページ)
先日12月4日(水)から翌5日(木)にかけての夜、ガザではイスラエル軍の攻撃によって最低でも39人が殺されました。この報道、日本でのメディア記事では見つからない。日本だけでなく、世界はガザを忘却しつつある。忘れてはいないとしても、ニュース性という観点からはガザでの殺戮への興味が薄れていると言っても間違いではないと私は思っています。
(ガザで最低でも39人が殺されたという記事はこちら。Dozens dead in Israeli strikes on Gaza; Palestinians say Amnesty ‘genocide’ declaration comes too late | Reuters)
アーティフ・アブー・サイフ(作家、2019年からはパレスチナ自治政府文化大臣)が著した『ガザ日記』を読む。
普段はパレスチナのヨルダン川西岸の町ラマッラーに暮らす著者アーティフは2023年10月7日、たまたま生まれ故郷であるガザ北部のガザ市近くのジャバリアへの数日の里帰りをしていました。15歳の息子ヤ―セルも一緒に。
その10月7日未明にハマース勢力よるイスラエル国内への侵攻があり、その報復としてイスラエル軍のガザへの大規模な攻撃が始まった朝、アーティフはガザ北部の砂浜で海水浴を楽しんでいたのです。それから、2023年12月30日、彼が息子ヤ―セルとガザ南部のラファ検問所を通ってエジプトに出国するまでの85日間、毎日つづった文章が『ガザ日記』です。
イスラエル軍によるガザでの大量殺戮はその後2024年に入っても続き、1年間/12か月が過ぎ、今日(12月7日)、昨年10月7日から数えて427日が経ちました。アーティフが体験した85日間は、427日のほぼ2割に当たります。2割の残りは8割。この日記で描かれた日々を耐え過ごす市井の人たちの暮らしが、その後の8割の中でますますにひどいことになっているかは想像に難くないことです。
水が足りない。食料が足りない。さまざまな燃料が足りない。寒さ(アーティフがガザを脱出した12月は、これからいよいよ冬本番で寒さが増し、さらに雨がその寒さに拍車をかける季節でした、そしてその2度目の冬がまた来ています)をしのぐための毛布が足りない。 寝る場所として必要なマットが足りない。テントが足りない。トイレが足りない、女性の生理用品が足りない。もちろん電力も足りない、インターネット/電話回線への接続もうまく機能しない。
情報が足りない。医療品が足りない、常備薬が必要な人にその薬が届かない。
そして、イスラエル軍があやつるドローンが常に空のどこかから音を立てている。夜になると激しい空爆が続く。戦車が町を破壊していく。
学校は破壊され、子どもたちの学びの機会もない。Pressと書かれた目立つ青いジャケットを着たジャーナリストやカメラマンが狙い撃ちされている。赤新月(イスラム社会の赤十字)の印をつけた救急車が戦車から砲撃される。病院が包囲され銃撃され病院内とその周囲に避難した万の単位の人たちが退避を強制される。
イスラエル側が通知した避難路上にイスラエル軍が設置したチェックポイントで身元確認がなされ、そこでは特に理由を示されることなく若い男性が拉致される(ガザの住民は、イスラエル政府が発行するIDの所持を強制されている、ガザはイスラエル領土ではないはずでは???)。15歳の息子と検問所を通過したアーティフは、イスラエル兵がチェックポイントを通過しようとする男性の個々のIDをチェックすることもなく、単にその外見だけで「テロリスト」か否かの判断をしていることを目撃する。テロリストと判断された者は、その場で拉致され、収容所へ運ばれいつ解放されるかもわからない。息子や夫を拉致されて、消息もわからず嘆く人たちも多くいる。
それでも。
アーティフがガザに幽閉された85日間、北部のガザ市周辺は壊滅的な破壊を受けたけれど、南部のハーンユニス市やラファ市への攻撃・破壊・殺戮はまだ途についたばかりでした。彼がラファへ避難したとき、まだ南部には公共バスが走っていたし、ガソリンは不足しても車はサラダ油を燃料に走っていました。おそらく、今、公共バスはその運営を停止し、ガソリンだけでなくサラダ油だって十分にはないはずです。
アーティフがガザを脱出した2023年12月30日以降、南部への攻撃はますます苛烈さを増し、ガザへの食料や燃料等の補給はますます細い糸と化している。つまり『ガザ日記』に記された残酷で非人間的な状況は、まだその初期に過ぎないのです。2024年は師走を迎え、ガザ大虐殺は2度目の冬を迎えている。かすかに入ってくるガザ事情は、すでに人の尊厳が無茶苦茶に侵害された残酷な状況に陥っているように思えるものです。
アーティフの実父は幼い日に1948年のナクバを経験しました。そして、この2023年の“ナクバの再来(強制移住)”をせめて拒否して、父親はガザ市郊外のジャバリアに居残りました。共に避難しようというアーティフの懇願を、父は拒否したのです。そして、『ガザ日記』の終盤の2023年12月末、高齢の彼は常備薬が切れ持病に苦しみつつ、まだ生きていた。あれから1年、彼は生きているのか? 生きていれば奇跡なのではないか。
『ガザ日記』には、2023年10月7日未明のハマース勢力らによるイスラエルへの奇襲については一切書かれていません。書かれていない理由のひとつには、アーティフがハーマスと対立するファタハ政府(パレスチナのヨルダン川西岸を統治)の閣僚メンバーのひとりであることがあるでしょう。彼の立場でガザ領域内でハマースに言及することは、最悪の場合は生死にかかわる危険もあるのだと想像します(ハマースによる処刑対象になるという意味です)。けれども、彼が描こうとしたイスラエル軍の攻撃の下に暮らす市井の人々にとって、10月7日の“きっかけ”の内容は重要なことではないのだとも私は本作を読んでいて思いました。だから、アーティフは“きっかけ”について何も書かないという選択をしたのではないだろうか。
2000年にガザに生まれたもうひとりのナツクサ
私には2000年に誕生した子どもがいます。男の子で夏草という名前です。
そして、同じときにガザにナツクサという名の男の子が生まれていたらという妄想から私は自由になれないのです。ガザのナツクサはどうしているだろうという思いに囚われているのです。
ナツクサが生まれる7年前、1993年にイスラエル国政府とPLO(パレスチナ解放機構)の間でオスロ合意が結ばれました。パレスチナ問題がイスラエルとパレスチナという二国家共存という解決に向けて合意したと世界の多くは理解した。ガザやヨルダン川西岸に暮らす“パレスチナ人”も、このオスロ合意を和平の進展と受け取った人が多数だったのです。けれども、その期待は裏切られる。象徴的なのは、パレスチナ領土を不法占拠するイスラエルの人たちによる入植地がオスロ以後にますます加速して増えたことです。
この明確なオスロ合意違反に対する国際社会からの非難を、イスラエル政府は黙殺しました。そしてパレスチナ内で発生する抗イスラエルのデモを、オスロ合意を受けてパレスチナ暫定政府が設立した警察が鎮圧するという喜劇?悲劇? やがて、そんな不法占領地(入植地)を守るような隔離壁がパレスチナ“領土”であるヨルダン川西岸の中に建設されていきます。
夏草が日本で、ナツクサがガザで生まれた2000年は、オスロ合意がすでに破綻したとパレスチナ社会では多くの人々に判断された年でした。そして、2000年後半にはパレスチナ側からのイスラエルへの大きな抗議行動(第2次インティファーダ)が始まります。パレスチナ和平への希望が決定的に消え去ったのが、夏草とナツクサが生まれた2000年に起こったことだったのです。
その後2005年にイスラエル政府はガザ内のイスラエル人不法占領地(入植地)、および軍施設を放棄しガザから撤退する決断をします。ガザに進出し生活を始めていたい入植地のイスラエル国市民からは当然に強い反発が起こりましたけれど、イスラエル政府は彼らに(パレスチナ領土である)ヨルダン川西岸の新たな不法占領地(入植地)を代替地として補償することで解決策としました。
イスラエル入植者と軍とがガザから完全に撤退したその後、イスラエル政府はガザを徹底的に封じ込める政策・作戦を実施したのです。
2005年以降、ガザはイスラエルとの境界を高い隔離壁に囲まれた天井のない監獄と化します。それまでイスラエル国内ではガザから毎日越境してやってくる労働者が多くいました。けれども、そんな労働者の移動もイスラエル政府は認めなくなります(マラウイやケニアといったアフリカ諸国、スリランカやバングラディシュといった南アジア諸国、タイやインドネシアといった東南アジア諸国からの出稼ぎ労働者がパレスチナ労働者の穴を埋めました)。
ナツクサが成長した2000年代のガザは、窒息していくガザだったのです。境界を超える物資の輸送はすべてイスラエルに管理され(つまり自由な貿易活動ができない)、飛行場もなく(1998年に開港したガザ国際空港、その建設整備には日本政府のODA支援も使われました、は2001年にイスラエル軍の空爆で使用不可となり閉鎖された)、漁民は2010年以降沖合3海里/5キロメートル強までしか行動できない(このラインを超えれば、イスラエル海軍によって無条件に射殺される危険がある、ちなみにオスロ合意では20海里/37キロまでの操業が認められていた)。失業率は40%を優に超え、若者には世界に開かれた未来などない。
この絶望の日々については、現代アラブ文学研究者である岡真理さんが2018年に世に出した『ガザに地下鉄が走る日』(みすず書房 )が詳細に描写しています。
2000年生まれのナツクサが、もしガザから一歩でも外の世界に出たことがあるとすれば、それはイスラエルに逮捕拘束されたからだったでしょう。その場合は、境界を出た先は収容所で、理不尽な扱い、おそらく拷問を含んだ、だけが記憶に残っているはずです。
そして、そんな記憶がないとすれば、ナツクサは生まれてから一歩もガザを出たことはない(日本に生まれた夏草は、幼いころから海外、たとえばカンボジア、に行く機会がありました、最近も香港に出かけたそうです)。冒頭にあげた、『ガザ日記』の一文の中でも、筆者アーティフは「ほとんどのガザ人はこの地区の外に出たことがない」と記しています。
2023年10月7日、ハマース勢力のイスラエル奇襲の際に、小さな動力をつけたハンググライダーが使われたという報道を読んだことがあります。この報道の正誤を私は判断できないままです。本当に使用されたとしたら、隅々までイスラエル軍の監視がいきわたっているガザのどこで飛行訓練がおこなわれたのだろうか? エジプトからの密輸トンネルを通って運ばれたハンググライダーでぶっつけ本番、飛行練習なしで飛んだのか? ハンググライダーそのものが廃品を利用したMade in Gaza つまり手作りのものだったのか?
そして、もしナツクサがハンググライダーにのってイスラエル奇襲に参加していたら、と私の妄想は続くのです。空を飛んで、高い隔離壁を超えていく。それがどれだけ“快感”だっただろうか? 快感だったに違いないじゃないですか? 24年間、壁の内側に閉じ込められていた青年があの夜、生まれて初めてその壁を越えたとしたら……。
壁を超えた後、彼がとった行動は、私にはよく見えない。殺したのか? 殺しただろう。 イスラエル側が発表したような、幼児の殺戮や、女性へのレイプがあったのか?(ハマス勢力側は、それを否定しています、岡真理さんはイスラエル側が発表したハマースの非道が、イスラエルがこれまでパレスチナ住民に行ってきた非道、たとえば1948年イスラエル建国時のエルサレム郊外のデイルヤーシン村でのユダヤ人武装組織による住民の虐殺事件、と酷似していることを指摘しています。つまり自分たちがやってきたことを「されたことにする手法」の可能性を岡真理さんは疑っているのです。
越境後の行為に関して、ナツクサはまだ黙秘を続けています(あるいは、ナツクサはすでに死んでいる可能性も高いでしょう)。
ナツクサは、(もし生きていれば)自分が加担した“暴力”を今どう振り返ろうとするのだろう。もちろんこの暴力の連鎖は2023年に始まったモノではありません。パレスチナ側とイスラエル側と、殺した数にはおそらく100倍近い違いがあるはずです(もちろんイスラエル側の殺戮が多い、イスラエル側がひとり死に、パレスチナ側は百人死ぬのです)。
私は、生まれてからずっと戦争の日々を送ったナツクサに「殺すな」と説得することができるのか? 説得できなかったから、ナツクサは闇にまぎれてハンググライダーで飛んだのではなかったか?
12月です。世界はクリスマスのネオンに包まれます。けれども、ババノエル(アラビア語でのサンタクロース)は昨年に続きこの師走もガザを祝福することはないでしょう。
ガザの旧市街にある教会に身を寄せている友人のフィリペにメリー・クリスマスと言いたくて電話をかける。しかし、ガザ市は相変わらず電波が届かない。ババ・ノエルは今年はガザに来ないだろう。そんな危険は冒さない。そりに乗った瞬間、頭を撃ち抜かれるだろうから。(『ガザ日記』409ページ)
追記
『ガザ日記』、中野真紀子さんの翻訳が素晴らしいです。
気になることをひとつだけ。著者アーティフはこの本の「あとがき」を2023年12月20日に書いています。そして彼が息子ヤーセルと一緒にガザを出たのは12月30日です。つまりアーティフはこの本が終結するその10日前に「あとがき」を書いたのです。彼が「あとがき」を書いた12月20日の日記内容を読むと、この日、アーティフは自分の友人がその息子3人と共にドローンミサイルで殺されたことを知ります。おそらく、アーティフは友人とその3人の息子の訃報を知り、自分と息子ヤーセルとの死を改めて強く意識し覚悟したのではないだろうか。
アーティフとアーセルは死にませんでした。けれども、この『ガザ日記』はやっぱり死者の書なのです。殺される者の書なのです。








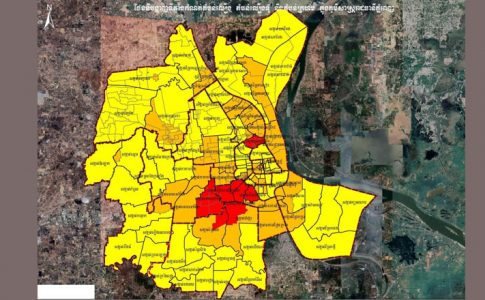





コメント、いただけたらとても嬉しいです