複雑系との遭遇、そして興奮
2000年、フィリピン南部、ミンダナオ島ダバオ市の教育事務所で働いていたときのこと。
20世紀の最後に働いたこのフィリピンで、仕事でインターネットを使い始めた。事務所でインターネットを使うのには、電話回線を使った。ぼくの世代であれば、インターネットに電話回線からアクセスする際の、独特なあの発信音、ピー クチュクチュクチュ、を覚えている人も多いだろう。
ぼくがインターネットを使っていると、上司のバルデラマさんが、「電話を使うから、インターネットを切れ」とガラス戸で仕切られた彼女の個室から目で合図を送ってくる。アイコンタクト。はいはい、切りますよー。
というわけで、どうしてもゆっくりとインターネットを繋ぐのは、同僚たちの勤務時間が終わる午後5時過ぎ、あるいは週末だった。皆が去った、あるいは週末の静かな事務所で、マニラや他の地域の教育事務所に入っている同じプロジェクトの日本からの同僚らからのメールを読んで、返信を書いていた。データ量の大きな写真やドキュメントの送受信にはとても気をつかったころの話だ。
「世の中には、複雑系という考え方が流行っている」と知ったのも、ようやく広がりつつあったインターネットでのコミュニケーションを通してだっただろう。経緯は覚えていないのだけれど、M.ミッチェル ワールドロップ著『複雑系―科学革命の震源地・サンタフェ研究所の天才たち 』(新潮文庫 2000)を日本から取り寄せて読んでみた。
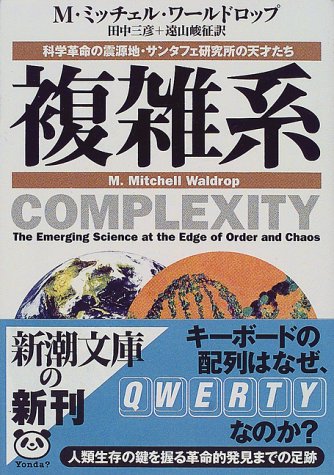
オォ!って感じだった。すごく面白かった。
「これって、今、自分がフィリピンでやっていること(教育支援援助協力)と、強く繋がっている」という感じがビンッビンッとして、興奮して読んだ覚えがある。
複雑系ってなに?って話をどうここで書きましょうか。
ある“場”があるとする。その場には、外部から複数の要因がかかわっていて、それが“複雑”にからまって作用している(開放系、他者準拠型システム)。さらに、その場では、そんな外部からの要因だけでなく、場そのものの変異が、さらなる変異を呼ぶ(自己準拠型システム)。場を動かす要因たちは、その場で和として働くのではなく、相乗効果を含んだ単純な和とは違った増減を示す(非線形性)。さらに、その場は、さまざまに変化する外部環境に適応するように、自分自身を自律的に制御しながら多様に変化し組織化していく(自己組織性)。そんな“場”が複雑系。で、人の社会は複雑系だし、そのときぼくが直面していた多くの課題・出来事は、自分がかかわっている場が複雑系であると理解することで、「そうだったのかぁ」と深くうなずける。
どうでしょう?うーん、わかったようで、わからない説明の見本のような書きぶりであります。
開き直りのための超特大ナイスな言い訳、あるいはポールのマリア様
で、ぼくの興奮の最大のポイントは「あぁ、オレのやっていることは、その結果は予測するのが極めてむずかしいことなんだ」ってところにあったのだと、今ふり返って思うのです。予測できない、それが当たり前、って開き直れたんだと思います。
それは、たとえば、うーん、なんか調子わるいなぁと思いながら人から薦められた医院に行ってみたら、「あなたは〇〇みたいだね」とお医者さんから伝えられて、え、そうなの?と思って〇〇について書かれた本を読んだら「ある、あるある、あるよー」って、目から鱗が落ちて、なんだぁ、オレ〇〇だったのかぁ、と、病名が定まって、ちょっと安心するってのと似ているような気がする。そう診断されても、調子の悪さが改善されるわけでもないのだけれど、でも、腑に落ちることで、なんか楽になったような気がする、っていうあれですよ。
医学や複雑系を研究する学者の人たちにとっては、そのレベルで安心されても満足できないわけで、やはり〇〇への治療法とか対処法とか、法則性とかを明らかにしたい、ってことになるのでしょうけれど、特に学者でもないぼくのレベルでは、なんだぁ、〇〇だったんだ、つまり「複雑系」の中で、もがいていたんだ!と思えたことが、興奮だったのです。
ぼくに取ってのキーワードは、「コントロールできないのだから、コントロールしなくていい」でした。おそらくそれまでは、コントロールしたくて仕方がなかったんだと思います。盤上を支配したくて、その支配権を獲得するための次の一手、さらに二手先、三手先を論理的に組み上げようと四苦八苦していた。
でも、そんなことにエネルギー使うのは無駄なんだと、複雑系の考え方は教えてくれたのです。「コントロールしなくていい」と思い始めると、いろんなところで力が抜け始めました。ようやくビートルズの名曲“Let It Be”の意味にちょっと手が届いた感じ(ぼくは、中学生ぐらいでビートルズと出会ったころ、あれはLP、LPと歌っている、つまりレコードの歌かと思っていたのでした、実話)。そうだ、あるがままでいいんだ、受け入れていいんだ、と。ポールマッカートニーにとっての“マリア様”が、ぼくにとっては複雑系だったのです。
「コントロールしなくていい」は、やがて「コントロールしようとしてはいけない」に、さらに「コントロールしてはダメ」と進化していきます。技術援助や教育の場で、「コントロールしたい」ことは山程あります。でも、コントロールできたときというのは、危ない。その場は満足できるかもしれないけれど、支配には必ず強い副作用が生じます。
自己満足に浸りながら援助者は去り、その後、副作用に苦しむのは支援された側です。多くは、誤解や勘違い、不必要な制度化、が生み出す新たな権威、による現状維持の圧力…。それだって、カオスの中の短期的な現象である、と言えないことはないですけれど、でも自分が「自己満足に浸りながら去りゆく援助者」って役どころでいいのかって思った。それは、避けたいでしょう?
そう思って、自分を、あるいは自分の周りで起きていることを観察すると、「コントロールしたい」意識がどれだけこの世に無駄に存在しているのかって気がしてきました。もうやめましょうよ、そういうのは、って思い始めたのです。
あきらめて、祈りますか、ね。
開発プロジェクトには、シナリオがあり、目標があります。当然、そのシナリオに沿って進めていきたいし、目標を達成したい。今や目標は必ず数値化されていますから、達成したい数値目標がある。つまり、それが「コントロールしたい」のそもそもの始まりです。
じゃ、数値目標は止めます、ってわけにはいかない。「援助は複雑系ですから、数値目標とかナンセンスです」と言えば、「そういうあんたがナンセンス!」。そんななかで、どうやって「コントロールしない」は可能なのか。
ものすごく開き直ったぼくの答えは「あきらめる」です。だって、仕方ないじゃない。
たとえば、ぼくが一番強く影響を与えたい相手側のカウンターパート。その人をぼくは選べない(選べたとしても、実は大差はないんですけれど)。とにかくどんな人と出会えるかはわからない。その人との相性がいいか、悪いか。いいと思ってたら、その人が病気で、代わりの人が来たりすることもある。今度は、相性が悪い。そんなことが、どうしたって起こります。だって、仕方がないじゃない。「強い人」「上手い人」なら、誰とでもそこそこ上手くやれるかもしれない。もちろん、そんな技術を持っているほうが、持っていないよりは、いい。だから、その技術を磨くことは大事。できるだけやる。でも、ぼくができるのは、せいぜいそこまで。
プロジェクトは多くの外部要因が関わり(解放系、他者準拠型システム)、プロジェクト内でもアクシデントは起こるし、おなじインプットでもタイミングによって変化するアウトプットによって次のニーズも変化するし(自己準拠型システム)、うまくいくときはインプットが見事にハマって倍々ゲームで成果が上がるときもあるし(非線形性)、さらにプロジェクト終了後もシナリオ外に勝手に動いて負にも正にも働く(自己組織性)。
「野となれ山となれ」ということをこの場で伝えたいのではないのです。結局、ぼくができるのは「祈り」みたいなことなのかもしれない、ってことが伝えてみたいのだと思います。やることはやる(でも無利しないほうが、いい、だって、無理すれば絶対にあとでその場に負の反動がでるから)、そのうえであとはうまくいくように祈る。2000年に複雑系を知って、「コントロールしない」を心がけるようになって、ようやく2010年に入ったころ「こんな感じでいいのかな」とたどりついたぼくの開発支援の哲学は、せいぜい、そんな感じで「祈る」ことだったように思います。そうしたら2014年に事故っちゃったぁ。
やれやれ…。双六でいえば、「始めに戻る」。でもね、それは30年前のスタート地点はもうかなり違う場所なんだと思っております。
どうぞ皆様、なにごとも「コントロールしない」って視点で、見てみてください。ちょっと新しい世界が見れるかもしれません。ぼくは、ちょっとそんなところがありました。
気持ちいい
それでもフィリピン後、2002年にかかわり始めたカンボジアでずいぶんと時間が経ってから、仕事仲間のK先生から「最初のころの村山さんは、やりたいことがたくさんあったみたいだからね、フッフッフッ」と笑顔で言われたことがあります。それはぼくには「たくさんのことをコントロールしたがっていたよねぇ ヘッヘッヘッ」と聞こえました。そうだったかもなぁ。そして、それは「ま、最近は、そこそこ力抜けてきたねぇ ホッホッホッ」という褒め言葉にも聞こえました。K先生から褒めていただけるとは、と、ちょっと嬉しくもなりました。とにかく、意識してからも、ぼくが「コントロールしたい」の支配から抜け出すにはずいぶんと長い年月がかかったみたいだったのです(おそらく油断すれば今だって)。
2012年末、ルワンダに向かったときのことを思い出すと、ルワンダで「やりたいこと」って特になかったんじゃないかしら。まぁ、まずは見てから考えようと思っていたような気がします。もちろん、プロジェクトにはやるべきことと(計画)と達成すべきこと(目標)は、ありました。でも、それはそれ、だったのです。なんか、あれは気持ちいい感覚があったなぁ。コントロールしないってのは、気持ちいいんですよ。














コメント、いただけたらとても嬉しいです