開発支援に失敗は許されない
フィリピンでODA(政府間援助)による教育支援プロジェクトの一員として働いていたときのこと。
日本のODA実施機関のプロジェクト担当スタッフが語った忘れられない一言がある。それは以下のような内容だった。
「ODAでは実験はしない。成果の上がるプロジェクトだけを実施する。ODAでは失敗は許されない。」
あくまでお茶飲み話のような場所で、それでも真面目にプロジェクトの成果について議論していたときの一言だったと思う。ぼくとしては、当時自分がかかわっていたそのプロジェクトの成果に、なかなか自信が持てない時期だったので、余計に印象に強く残っている。
率直に書けば「そうかなぁ、今のプロジェクトは実施決定の段階で、絶対に成果が上がると確証されていたのかなぁ。そのわりには、いろいろと問題が起こっているなぁ」と、そのときのぼくは思ったんだ。
今でもそうだろうと思うけれど、評判のいいプロジェクトは、成功例として他国のプロジェクトにも影響を与える。中には、一大ムーブメントを起こすこともある。他のセクターのことはよく知らなけれど、教育という分野では、そういうことはわりと多く起こっている。
たとえば、A国で、ある教育開発支援プロジェクトがいい成果を出し、それが高く評価されたとする。すると、それと同じようなプロジェクトを、A国と同じような社会背景を持つ同じ地域のB国、さらにはC国で実施することになる。A国でのプロジェクト関係者は、その成功事例を他国に普及させる役割を果たすことになる。
しかし、ある国や地域で成功したプロジェクトが、他の場所で成功するとは限らない。それだけ世界は多様で、一様のやり方が常に正しいわけではない。だから、どのプロジェクトにも必ず実験的な要素は残る。実施する前から100パーセント成功するとわかっているプロジェクトなど、存在しなだろうとぼくは思う。
また、何をもって成功というのかも簡単ではない。開発の業界でも、その評価方法を巡ってはいろんな議論があったし、ある。そこでは客観性がキーワードだ。だれが見ても納得できる成果とは何か?そんな中で、いろんなプロジェクトのフレームワークが使われ、成果を数値として“見える化”する工夫が検討され続けている。
ぼくがかかわってきた授業法改善のような取り組みで、その成果をどう測るかも簡単ではない。たとえば、日本の学校教育にしても、年を重ねるごとに教育の質は高まっているのだろうか。新しい教授法が開発され、パソコンやインターネットが教育現場に導入されて、さて、それでどう教育の質が向上し、生徒の学習成果が高まったか。それを数字で示せているのか?決定的な示し方は確定していないだろう。
進む“見える化”への模索、でも?
教育の目的からすれば、最終的な受益者は学習者である生徒で、たとえばプロジェクトで教員の授業法が改善されれば、教室での生徒の学習効果は上がるはず。それをどうやって測って、客観的な数字として提示できるのか。さらに、教育の質向上が、具体的にどう社会に貢献するのか。援助にも“説明責任”が問われる中、教育援助にかかわっている専門家、コンサルタントが、このことに多くのエネルギーを使い、政府(と納税者)やスポンサーを納得させるために努力している。
たとえば試験のパフォーマンスが上がるなどが指標として考えやすいように思いがちだが、それも簡単ではない。これまで存在する卒業試験などの国家試験を指標として使えればいいけれど、国家試験の問題の質から再検討する必要もある。つまり、暗記重視の試験を行っている限りは、授業法が変わった成果を国家試験で測れるわけでもない。
さらに国家の学校教育の役割には、公的セクターに優秀な人材を送り込むための選抜機能があった。公的資金・資材を投入した最高学府に到達したエリートは、政府で働く人材となることが期待される。学校教育制度というのは、選抜のシステムをどうしても内包する。
卒業資格試験などの国家試験の結果を教育の質の向上の証明に使いにくい理由のひとつがここにある。国家試験は、受験者全員の質が向上することを計測するようにはデザインされていない。全員が満点をとったら、選択機能が働かない。
だから、プロジェクトは、独自に事前試験と事後試験を実施することもある。そして、そんな試験は、ある傾向を示すようにデザインすることも可能だ。改善した部分だけにしぼった試験を行えば、事前と事後で差が出るのは当たり前でもある。きちんと成果が出たように見える指標を作り出すことは、コンサルタントの腕の見せどころでもある。
米国などで語られている警句に次のようなものあるらしい。〈統計はビキニ型の水着に似ている。さらけ出しているようにみえるが、肝心のところは隠されている〉[i]。本当にそのとおりだとぼくも思う。援助の現場で起こっていることには、統計で示される論理的構造的な理解の仕方に対して、より直感的メタファー的な、つまり経験的で主観的な理解も有効だと思うことが多い。ただ、それは「役に立たない」指標だ。主観的に「結果は出てます」と言ってすむほど、援助の世界も甘くはない。
そんな援助業界のなかであくせくしているとき、写真批評家の竹内万里子が、批評家として写真を見ることを次のように書くのに出会うとき、ぼくの心は揺さぶられる。
一つの写真に耽溺し過ぎることなく、状況を見渡しながら複数の写真の間を渡り歩くこと。その目配りの良さや知識の豊かさ、切れ味の鋭さを追求すること。どのような理由であれ、批評家という肩書を自分に許した以上、それは必要な所作なのだと自分に言い聞かせながらも、つねに後ろめたさがつきまとった。写真を語るという行為が、もしそのようなことでしかないのだとすれば、あまりにも虚しい。気がつけば、はじまりの問からずいぶん遠いところへ来ていた。[ii]
文中の「写真」を援助やプロジェクト、「批評家」を援助コンサルタントや援助専門家に置き換えれば、これは我が身のことではないかという思いに囚われる。敢えて、書き換えた文章を作ってみよう。
一つのプロジェクトに耽溺し過ぎることなく、状況を見渡しながら複数の支援の間を渡り歩くこと。その目配りの良さや知識の豊かさ、切れ味の鋭さを追求すること。どのような理由であれ、開発専門家という肩書を自分に許した以上、それは必要な所作なのだと自分に言い聞かせながらも、つねに後ろめたさがつきまとった。開発援助を語るという行為が、もしそのようなことでしかないのだとすれば、あまりにも虚しい。気がつけば、はじまりの問からずいぶん遠いところへ来ていた。
援助プロジェクトを受注し、求められる成果を(数値で)示すことに追われていると、「はじまりの問いからずいぶん遠いところ」に行ってしまうことは、ある。
あるいは、編集などを生業とする若林恵の次の言葉もそうだ。
自分になんの感動の体験もない人間が、もっともらしく「ユーザー・エクスペリエンス」を語り、数字しかあてにできない人間がしたり顔で「顧客満足」を論ずる。それによっていかに現場がモチベーションを奪われ、クリエイティヴィティが削がれ、結果どれだけ多くのリスナーが離れていったことだろう。そりゃそうだ。そんな連中がつくったものにいったい誰が感動なんかするもんか。[iii]
自分になんの感動の体験もない人間が、もっともらしく「目に見える成果」を語り、数字しかあてにできない人間がしたり顔で「説明責任」を論ずる。それによっていかに現場がモチベーションを奪われ、クリエイティヴィティが削がれ、結果どれだけ多くのリアリティが失われていったことだろう。そりゃそうだ。そんな連中がつくったものにいったい誰が感動なんかするもんか。
援助プロジェクトにも、大小あれど、感動は必須だ。
援助は巨大産業
それでも………。評価の数値化といった開発援助業界内の知恵比べのような過程も、越境のひとつのあり方、テクニックと思えば、思えなくもない。数値化であれなんであれ、援助がひとつの越境行為なら、その行為を成立させる技が必要なんてことはいくらでもあるはずだ。数値化もそのひとつと考えれば、越境者はその技を磨けばいい。
実際、援助という越境行為には十分な予算の出し手とその使い手が必要で、そこではすでに多くの支援する側の人たちが、その生活を「援助」に依存している。援助は、巨大産業だ。援助を受ける側は常に持続的な発展性を求められるけれど、援助という産業で稼いでいる側が、援助産業の持続発展性を求めているんだ。援助がなくなったら、世界中で何万人も失業者が出ることになる。
さて。
「ODAでは実験はしない。成果の上がるプロジェクトだけを実施する。ODAでは失敗は許されない」という言葉を先に紹介した。実は、この言葉には省略した一言がある。それを加えてみる。
「ODAでは実験はしない。成果の上がるプロジェクトだけを実施する。税金を使う以上、ODAでは失敗は許されない」
税金。血税と呼ぶ人もいる。だから、海外援助の問題は、日本の社会全体にも関係している。税金を使う以上、ODAに失敗はゆるされないのか? ぼくの答えはNoだ。(以下、続く。続きは11月26日に投稿予定です。)
[i] 東京新聞 2019年1月12日 コラム「筆洗」より
[ii] 竹内万里子/著 2018『沈黙とイメージ 写真をめぐるエッセイ』赤々舎 9ページ
[iii] 若林恵/著 2018『さよなら未来 エディター・クロニクル2010-2017』 岩波書店 93ページ











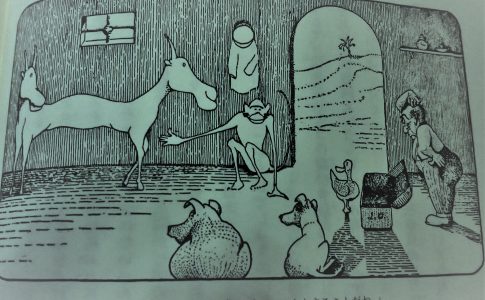


コメント、いただけたらとても嬉しいです