EDSA革命
フィリピンの首都マニラを囲むように走る大通りEpifanio de los Santos Avenue(スペイン語)は、略してEDSAと呼ばれる。日本であれば、エドゥサ、あるいはエドサと書かれることが多い。ひどい交通渋滞でも知られるこの大通りは、フィリピン現代史では大きな役割を果たしてきた。
1965年に始まったマルコス大統領政権は徐々に独裁性を強め長期政権となった。そのマルコス政権を倒したのが、1986年のピープルパワー革命だった。この革命では100万人を越える市民がEDSAに繰り出した。この人々の大きなうねりが20年以上続いたマルコス独裁を倒し、マルコス夫婦は大統領宮殿から米軍のヘリコプターで脱出し亡命するという、劇的な結末を迎えた。
この革命は、EDSA革命とも呼ばれ、当時の日本でも大きく報道された。そのとき大学生だった私も、大学構内で学友たちとフィリピンからのニュースについて興奮して語り合ったことを、今もよく覚えている。
マニラとダバオの“温度差”
その後、私は1997年からフィリピンで実施されていた理数科教育改善計画プロジェクトに関わることになった。最初の1年はマニラの教育省で、それから3年近くを南部になるミンダナオ島ダバオ市にある地方教育事務所で働いた。
そのダバオに勤務中の2000年1月、またEDSAに数十万人の民衆が集まった。当時のエストラーダ大統領が不正貯蓄疑惑で国会から弾劾されたことを受けて、大統領の辞任を求めて集まった人たちだった。この反政府活動はピープルパワー2とも呼ばれ、エストラーダ大統領は世論の波に押されて失脚した。
このとき、ダバオの事務所内のテレビは勤務時間中もマニラのエドサ通りでの反政府運動を映していた。普段は部屋の隅にあって昼休みだけバラエティー番組を流していた、けして映りの良くない大きな古いカラーテレビが、そのときは事務室の真ん中にどんと置かれた。その画面では、エストラーダ辞任後に大統領に就任することになるアロヨ副大統領が、大歓声をうけながら大統領の不正を厳しく糾弾していた。テレビの中では、1986年のビープルパワー革命が再現されていたし、日本でもそう報道されていたはずだ。
しかし、事務所でもダバオの町中でも、マニラとは違いむしろ大統領に同情的な声が多い印象を私は持った。同僚のコラは、「確かにエラップ(エストラーダ大統領の愛称)は良くないことをした。けれど、あんなこと政治家はみんなやってきた。巨悪は他にあるんだ」と熱のこもった口調で私に語ったものだ。そこには映画俳優出身で庶民派といわれたエストラーダへの親近感とは別に、中央マニラのエリート支配に対する反感があったように思う。ダバオでも若い学生らがエストラーダを糾弾する集会を開いたけれど、それを見る大人たちの目は冷静で、マニラの熱狂はそこにはなかった。
ミンダナオアン
教育省地方事務所の同僚らによれば、ミンダナオの人はマニラ中央政権に対して批判的な人が少なくなく、自主独立の気概に富み、ミンダナオ人(Mindanaoan)という言葉があるぐらいだ、と説明してくれた。ミンダナオ島南西部のモロと呼ばれるイスラム勢力とフィリピン中央政府との軋轢は知られているけれど、それとは別にキリスト教徒の中にも、ミンダナオ人としてのアイデンティティが育っているということらしい。
フィリピンという国は、スペイン植民地の時代に作られた大農場の所有者から繋がる数十のとても豊かなファミリーが現在も国土の半分以上の土地を所有し、持てるものと持たざるものの格差が歴然と存在するところだ。社会的階級が固定し、富める家族の子どもたちはその富を相続し、貧しい者がそこに食い込むのはほとんど不可能だ。「国境を超えるよりも、階級を超えるほうが難しい」ということを私はフィリピンで強く実感した。
そんなフィリピンで、ミンダナオ島はフィリピン独立後に多くのキリスト教徒がフィリピン中央部などから移住してきた二十世紀の新天地だった。明治期大正期の北海道をイメージすると、フィリピン現代史でのミンダナオ島の立ち位置を理解しやすいかもしれない。まだ支配層が支配しきれない土地がそこにはあった。それもあって、ダバオはフィリピンを牛耳る富める数十のファミリーへの反感が強い土地柄となった。
例えれば、マニラとミンダナオ島の関係は、一八世紀の英国と独立前の米国との関係にも似ている。北アメリカ大陸では、欧州からの移民が先住民を西に追いやりながらやがて欧州から独立し米国となる。ミンダナオ島でも、キリスト教徒が移住し、先住民であるモロ(イスラム教徒)の土地を奪う一方、キリスト教徒の中にも遠いマニラの支配を快く思わない気持ちが育つ。
ダバオで現職教員研修を実施していて面白いことに気がついた。フィリピンの教員研修では通常プログラムの最初にフィリピン国歌を流す。ダバオでは国歌の後に、ミンダナオの歌というのも流れる。面白いというのは、参加者の中にフィリピン国歌には口を固く閉ざし、ミンダナオの歌には大きく唱和する姿が何人か見られたことだ。なるほどねー、これがミンダナオアンの心意気かぁ、と思いながら彼らをちょっと頼もしく見つめたものだった。
国歌より、アナック(息子よ)のほうがずっといいと思うけど
話は飛ぶけれど、2020年に予定されていた東京オリンピック・パラリンピックに備えて、「私たちの小学校は〇〇〇〇(どこかの国名)を応援します」として、〇〇〇〇からやってきた選手たちと交流する活動が準備されていたはずだ。2021年にオリパラが開けれれば、そんな小学校では応援国の国歌を日本の小学生たちが歌って、選手団を歓迎するはずだ。
けれど、いろんな国の状況を知ると、実はそれぞれの国にはそれぞれの事情があることがわかってくる。その国の国歌を素直に歌えないような人たちの存在もある。どうやら他国の国歌をよその国の人が歌うのは、やはり無邪気に過ぎるんじゃないかとも思う。もちろん儀式として尊重し合うという態度が必要なことはあるとしても、市井の人たちの交流の場ではむしろ“国家”は少し後ろに控えてほしい。フィリピンであれば、勇ましい国歌よりも、“アナック(息子よ)”というタイトルの、現在も広く歌い継がれているフェレディーアギラの1977年のポップソングの名曲、哀切なメロディーがとても美しくあなたもどこかできっと聞いたことがあるはず、を歌ったほうが、選手団にはよっぽど喜ばれるのは間違いないと思うんだけれどなぁ。
(アナック、Youtube より)
https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%83%94%e3%83%b3+%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%83%e3%82%af+%e6%ad%8c&view=detail&mid=7B4FF79DEA549A2B50487B4FF79DEA549A2B5048&FORM=VIRE













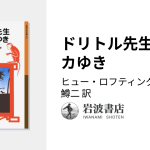
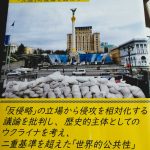

コメント、いただけたらとても嬉しいです