自ら死を選ぶ気持ち、行為、……
Aさんがいる。Aさんの心には「死にたい」という気持ちがあるとする。
理由はきっといろいろあるよね。大きな失恋や失敗、虐めにあっている、病気やケガ、何か大きな喪失感、絶望感、もしかしたらはっきりした理由はないけれど、でも漠然とした死への誘惑感が拭えないってことだってあるかもしれない。
実際のところ、「自死」を妄想・夢想したことがないなんて人、いるのだろうか? 「もう、死んじゃいたい」「消えてしまいたい」って思ったことがある人、口にしたことがある人が全員その思いや言葉に責任を持たなくてはいけない、つまり自死しなくちゃいけなかったら、おそらく人類はあっという間に絶滅だよねぇ。人は、落ち込み、立ち直り、ふらふらとしながら、でもだいたいは死ぬまで(自死ではない死ですよ)生き続けるもんなんだろうなぁ。
多くの人が、「死んでしまいたい」という気持ちを妄想の域で留めるとして。
けれども、もしAさんがひとりで死への階段を駆け上がってしまうとして、それを止めることは誰にもできないのではないか。
死の誘惑に囚われてしまった人が自らの命を絶つ行為を自らなすことを完全に無くすことはできない。また「死にたい」という思いを、その心を持つ本人以外の他者が否定しきれるものでもない。本人以外の他者は、どんなにその人に近しく親しい人でも、ただ心配するしか他はない。ぼくらは、愛する人の自死すら止められない無力な存在なのです。せめて、死なないでと祈り懇願するしかできない。
自殺してしまった人が罪に問われるか? 私の知る範囲で、日本の法律ではそのような規定はないのではないか。亡くなってしまった人が、罪を償いようもない。未遂ならどうか? もしかすれば、治療として監視下に置かれる措置というのはあるだろうけれど、それも罪の償いではない。
キリスト教やイスラム教では、自殺は神に対する大きな罪で、死後に救われないという大きな罰を受けることになるらしい。そんな信仰が、自死へのブレーキになるってこともあるでしょう。それはそれで、良し。もちろん、だからといって「自死を禁止する宗教」が素敵とか、エライとか、そんなわけでもないし(あくまで当社比ですけど、ね)。
さて、Aさんでない誰かがAさんが死へ進むことを具体的に支援してしまえば、それは現在では法律上の罪となることがある。自殺の幇助は、多くの社会で許容されないって理解してもいいのだろうと思います。
一方で、現在の世界では状況によっては「死を選ぶこともいたしかたない」と社会的に認められるケースも生まれつつある。たとえば、ひどい痛みに耐えなければいけないようなケース。この苦しみから逃れるためには死しか残されていないというようなケース。あるいは、延命治療を選択しないということも、間接的には自ら死を選ぶということ。医療の進歩は私たちに長命をもたらしつつあるけれども、一方で自分の意志では勝手に「死ねない」「死なせない」というような状況も産み出している。となれば、当然それを拒否するという判断も出てくるよね。「生き続けること」すら含めて、他者からの強要って嫌なものだから、拒否する気持ちはわかる気がする。
公的に自死を認めるということは、その自死を公が管理するということ。このような事例では、実際に具体的に誰かの自死を幇助することを社会から許された人が必要になる。死に向かうための薬や機器の提供があって、資格者は医療専門家だったりする。
たとえば延命を拒否するにしても、そのためには本人の、あるいはそれに代わりえる人の「署名」が求められる。そういう時代にぼくたちは生きている。
さて、障害者世界では自死の問題はもう少し複雑になる。その理由のひとつとして、障害者の中には「死にたい」とどんなに思っても、自分の行為として自分の命を絶つことができない種類の障害を持つ人もいるから。
そんな人が自死を選ぶためには、どうしたって他者の助けが必要になる。けれども、先に書いたように、自殺の幇助は社会的に許されない行為なわけで、つまり健常者には“選択可能”な「死を選ぶ権利」を行使できない障害者がいるわけです。
健常者の自死が完全に防げないということは、健常者ならば唯一無二である本人の「死にたい」という意思が発動することは常に可能で、つまりは自らの手で命を絶つことは許容されているということ。それならば、障害者の自死も同様に許容されるべきではないか、という理屈が生まれる。それでも、それを幇助する側に立てば、自分以外の誰かの死を支援するということは犯罪行為になる可能性が高いし、さらに幇助者自身の大きな苦痛が導かれる可能性も大いにある。自分以外の他者を巻き込んでまでして自死することが、自分で自分を殺せない者には許されるのか?(もちろん、健常者であろうと障害者であろうと、それが自ら行われるとしても、どんな自死も必ず他者をまったく巻き込まないなんてことはありえないのだけれど)。
それでも、ここ最近の欧米から届くニュースによれば、「自死する権利」は徐々に拡張する傾向にあるのは確かなことだ。日本社会でも、高齢者や障害者といった、多数派である「健常者」から外れる人たちの「死を選択する権利」を求める声は高まっている。繰り返しになるけれど、そういう時代にぼくたちは生きている。
なぜ「死を選択できる社会」を警戒するのか?
端的に言って、障害者世界の住人が「自死する権利」の広がりに対して警戒する理由は二つある。ひとつは「自死の選択」が認められる社会になれば、健常者から外れる人たちに対して「なぜ、あなたはそうまでして生き続けているのか?」という声が生まれることを危惧するから。もうひとつは、「なぜ、あなたはそうまでして生き続けるのか?」という声が存在する社会では、公的な医療福祉はけして拡張充実しないだろうことが予測できるから。
21世紀も四分の一が過ぎた今日、日本国の都心の公共交通を始めとするバリアフリーの拡張は、世界的にみても進んでいるほうだろう(より進んでいる国や地域はもちろんあるにせよ)。あるいは、重度障害者の介護に必要な公的支援制度も、24時間介護支援の実現がなされている日本社会は、世界的にトップクラスといっても間違いではないはずだ(こう書くと、「地域によってはまだ十分な24時間介護は実現されていないという実例が日本国内から山ほど出てきそうだけれど、けれども、その人たちがそれぞれの地方自治体と真剣に協議し、充実した介護の実現に向けて闘える状況があるということについては、やはり世界のトップレベルと呼んでよいと思うのです)。
バリアフリーや公的介護制度の拡大・充実は、今から半世紀前の1970年代に始まる障害者の権利拡張のムーブメントが背景にある。そして、そのムーブメントを主導した第一世代の訃報が毎年のように届く。そして、まだ存命の彼ら第一世代と彼らを支えた支援者たちが不安に思うのが、障害者の権利拡張につながるムーブメントの“後継者不足”のこと。
後継者不足は、SNS世代の誕生も背景にありそう。SNS(インターネットによるソーシャルネットワーク)の拡充によって、これまで以上に出る杭を叩きやすい社会が生まれている。もちろん、障害者目線からのクレームを広く社会に表明しやすくなった面もSNSはもたらしてはいるけれど、それ以上にSNSが生み出した弱者を叩く無名多数の存在が障害者の社会的運動を担う若い人材の出現を妨げているのではないか。だってね、20世紀後半の障害者運動の先導者たちは、100%と言っていいほどみな「出る杭」だったのだから。
さらに経済危機・経済縮小がもたらしやすい“社会の保守化”が弱者の生きやすい社会の創造には逆風になる。すでに達成された福祉制度ですらその継続は怪しく、やがては減退に転じるのではないか。将来へのそんな不安を、どうしたってぬぐい切れないのが障害者世界の住人なのです。
もちろん、「誰にも自死する権利はある」のかもしれない。積極的に認めようと認めまいと、どうしたって自死という行為は社会にある。
と、11年前に障害者世界にやってくる前のぼくだったら、そこまでで思考は止まっていたかもしれない。けれども、せっかくやってきた障害者世界なのだから、自分の考えをもう少し前に進めてきたはずなのです。続けます。
そしてね、「自死とは、本当に自らの意志としての止むない選択なのか?」という問いがでてくるわけです。もちろん、耐えがたい痛みからの解放を望む、なんてケースは、自らの意志として「死にたい」なのかもしれない。けれども、もしその痛みを緩和する医療がすでに存在して、その医療に到達できる人と到達できない人がいるとしたら? 「痛みに耐えられないから死にたい」と思うのは、後者だけが強いられる決断だっとしたら? 「死にたい」の有無の背景には明らかな経済格差があるとしたら? 一方の人は、痛みを緩和し手に入る日々をそれなりに楽しめ、一方の人は、痛みに苦しみ「死をこい願う」としたら、それはあまりに不平等ではないのか? つまりこの場合、自死を願う人は、貧しさの結果として自死に導かれた、とは言えまいか? もしそういう状況があるとすれば、それは自分の意志によって選択された死なのか? ちなみにこの段落での「痛み」はあくまでメタファーであって、高価な薬でもって左右される痛みがあるかないのか、じっさいのところはぼくはよく知りませんよ。
では、メタファーとしての痛みに代わる実際とはなにか?
障害者の心に「死にたい」という思いが去来するときに、その背景に「迷惑をかけたくない」という状況がともなうのは、ごくごく普通に起こっていることなんじゃないか。家族に迷惑をかけたくない、から、死ぬ。その迷惑とはどんな迷惑なのか? 介護の大変さを家族が背負わなくてはいけないってことだよね。肉体的に、精神的に、経済的にかかる負担が気になる。この負担を軽減すれば死ななくていいわけだ。つまり、介護が分散できれば、迷惑は減少し、その人は死ぬ必要はなくなるってこと、だよね。つまり、介護を家族以外に依存できる人は死なない。家族のみに介護を託せなければ、死をえらぶってこと。そこに格差はきっとある、あるいはあった。
もちろん、「死にたい」の背景には、健常者のように動けないことへの絶望や失意ってこともあるかもしれない。その場合、ときには「その気持ちはわかるよ」という思いがぼくにはある。けれども、その負は多くの障害者が乗り越えてきた。その実績は確実に高く積み上がっているし、AIはじめとした技術の進歩によって乗り越えるべき壁は確実に低くなりつつある。
だから、ごく端折って書けば、「迷惑」の壁も、低くなりつつあるはず。壁を辛抱強く叩き壊してきた先人たち、その支援者たちに心からの敬意と感謝を送りたい。
けれども、「死ぬ権利」拡充がこれまでの先人たちの努力に水をかけようとするのです。そうして生を拡張してきた人たちが「どうしてそうまでして生きるの」という声に怯える。選択肢が公的に用意されれば、「死ねばいいじゃん」「なんで死なんの?」とつぶやく無名の輩が、必ず出てくる。しかもかなり大量に。そして、そんな無名の声の波に乘って、「死を選ぶ権利」をきれいなオブラートに包んで政策化しようとする政治がきっと出現する。それは昨今の弱者への無礼な攻撃を許容する社会をみれば、火を見るより明らかではないのか。
だから、安楽死を合法化した国の実情を報告する映像番組を見た後に、次ような言葉がSNSを流れる(以下三段落、実際にFBの中で流れたコメントを、無断使用しています)。
『NHK BS1で9月30日再放送された「安楽死のある国」を見た。カナダのオンタリオ州で、安楽死が法制化されてから、安楽死者の数がどんどん伸びているということだ。在宅介護を求める書類は膨大なのに比べて、安楽死を求める書類は2,3枚で済むという事だ。一度法制化されてしまうと、国は社会サービスにかける予算を大幅に少なくしてしまう。日本でも尊厳死を法制化させようとする動きがあるが、絶対それをさせてはいけない。』
『この番組、私も視聴しました。
パーキンソン病の患者さんが歩行が難しくなってきて骨折を繰り返すようになり、入院先から安楽死をする医師に電話して「もう死にたい」と訴える。そうすると医師は「それはすぐに対応が必要になるかもしれない」と安楽死の準備を進める、というシーンがあり、絶句しました。
その前にいくらでも、骨折させないような支援ができると思うのに、そこをすっ飛ばしてしまうのだと。なんて簡単に死に向かわせてしまうのだろうと恐ろしくなりました。』
『介護を受けながら暮らせる場所がない。だから死ぬ決定をするしかない。死ぬ選択肢が現れ、ますますケアの質が落ちる。ひどいケアしか受けられないなら、死んだほうがましになる。
他人事ではない。日本でもこれが始まるかもしれない。』
安楽死、尊厳死、そんな言葉が必要のない社会ならいいのに。
もちろん、それが理想論なのはわかる。安楽死を求める人から「あんたにわたしの置かれた状況がわかるのか、この気持ちがわかるのか」と言われれば、その人に対してぼくは黙り込むしかない。でもね、それはやっぱりミクロな視点。もちろん一つ一つのミクロな視点はとっても大事。だけど、マクロの、大きなものの見方も大事なんです。だから、やっぱり安楽死や尊厳死を求める声には、慎重に向き合うことになる。それが弱者の条件反射ってものだろう。
夫婦別姓の権利と、死を選ぶ権利の違いは?
「死しか救いがない人が、その選択をする」、だから死を選べる制度ができたとしても「死にたい人だけが死を選ぶ。生きたい人は生きられるからなんの心配もいらない」という声が聞こえてくる気もする。
そこでふと思ったのですよ。「死を選択する」ことを法制化することと、「夫婦別姓を認める」ことの法制化とどこが同じで、どこが違うのかと。どちらも、「選択すること」を認めてくれと言っていて、すべての人が「死を選ばなければならない」とか「夫婦別姓を選ばなくてはならない」ということではない。あくまで、それぞれの生き方の権限の拡張を、公に支援してほしいということになる。
ぼくは、前者の課題では「死が公に選択可能になり、それを支援する専門職が生まれる」ことに忌避感を覚えていて、後者では「婚姻時に夫婦別姓を選べないのは不都合である(夫婦別姓を強制されるのは、嫌だ)」という価値観の持ち主であるわけですよ。前者では、そうしたい人の選択だけでは収まらないことを心配し、後者では選択できるようにしてと考える。う~む、やれやれ勝手なもんだよね。
こんなに苦しいのにそれでも死ねないって状況があるならば、それは「生きるのを強制されるのは嫌だ」と考えたっていいじゃんね。そして、確かに「強制」されたら、きっと嫌だな。母も妹も、私のパートナーであるサンワーに「哲也はわがままだ」「お兄さんはわがままだ」という類のことを語ったことがあるらしい。はい、否定できません。我がままで、天邪鬼でありますわたくしは、強制されるの苦手なんです。
でも、「生きることを強制される」以上に「死を強制される」のはたまったもんじゃないな。そして、選択的死を公的システムの中にはめ込むことが、間接的であるにせよ「死を強制される」ことにつながることを私は恐れている。そして、死を強制されるのは、現在、そして将来的に生産性が低い弱者と相場は決まっているってのは、歴史から学べば明らかなわけですよ。障害者や高齢者に刃は向く。
婚姻時に、夫婦同姓を選ばないカップルに、同姓を選ぶカップルと同等の手当てをするという制度が実現したとして、同姓カップル(あるいは愛する人と同姓になることを将来に夢見る人たち)は「別姓を強制される」と怯えるだろうか? カップル両者の価値観が違う場合は、そういうケースも出てくるかもね。パートナーから「別姓にしましょう」と提案されて、天地がひっくり返ってしまうって人が出てくることが絶対ないとは言えないですよ。でもさぁ、それはやっぱり「死ぬことを選ぶことを強制される」深刻さと比較すると、やっぱり笑える範囲じゃないかな。当事者同士で決めてくれと突き放してもいいんじゃないかと思える。別姓云々が「日本の文化を覆す大事である」とはけっして思えないのです。
そう、一番最初に書いたように「自死は止められない」、つまり人は自ら死を絶つことを選択肢として持っていることを否定しきれないわけです。ですから、弱者に対して優しく安全な社会であれば、「死を選ぶ権利」とそれに対応した制度作りに反対する理由はないかもしれません。障害や病苦が自死を選ぶきっかけになることだって完全否定なんてできるわけもないのだから。
けれども、どうも人類社会はまだそれほど弱者に優しくできていない。弱者に優しい社会に向かう傾向はあるように感じるけれど、まだ人類全体の総意・価値観を育て上げるだけの経験が足りない。だから、やっぱりまだ「死を選ぶ制度」の拡充には早すぎるんじゃないのかなぁ。どうしても心配なのですよ。この思いは、弱者でない人たちには理解できない部類のことなんだろうか?
でも、死を選ぶ人たちも弱者だろうな。それとも、それは強者の特権と化しつつあるのか? 生きたいのに殺される人たちが世界には今日もまだ多数いるこの現在、積極的に自死を選べる人たちは、弱者なの、強者なの? さて、どちらなのでしょう?
それにしても、安楽死や尊厳死を巡る議論は書いて読み直してとするのはとても気が疲れます。油断なく厳密な書き方をしないと、すぐに足をすくわれてしまうように思えてしまうのです。ということで、まだまだ勉強中なのです。きっとまた書きます。今回はこのへんでご容赦。
ではでは、また。













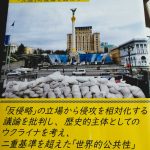

コメント、いただけたらとても嬉しいです