最初はだれもが旅の初心者なのです
九月下旬の一週間ちょい、プノンペンから東京へ飛び、浅草を拠点に過ごしていました。
上京すれば必ず会って話す旧友がいます。今回も顔を合わせました。その彼が私に『一億年のテレスコープ』(春暮康一著 早川書房 2024)というSF(サイエンスフィクション)をくれました。SF雑誌でベストSF2024に選ばれたと帯にある。
その旧友の大学4年生のお子さんが、この夏に生まれて初めて国境を超える旅に出かけた。
旧友は、三浪して入った大学生時代に、まずインドに出かけ、さらにチベットに出かけた。チベットではチベットの人たちが北京政府の弾圧に抗した小さな反乱にも遭遇している。そこで彼は誰かに「あなたは漢人に間違えられそうだから、気をつかたほうがいい」なんてことも言われた。たしかそのときのことだろうと思うのだけれど、彼はチベットからネパールに抜ける際、ヒマラヤ山中の峠を途中徒歩で移動するなどの小さな冒険も体験している。ぼくたちが同じ高校を卒業したのは一九八三年三月だから、彼がインド亜大陸あたりをうろうろしていたのは八〇年代後半ということになる。
よく彼の旅話しを聞いた。羨ましく聴いた。彼によれば「インドに行って、人生が変わる奴と変わらない奴がいる」とのことで、そして、彼はぼくを指さして「お前は変わらないタイプだな」と決めつけた。ふーん、そんなものかと思うだけで、決めつけられたのが嫌ってこともなかった。そういえば、彼自身はどうだったのか?おそらく、彼もそれほどは「変わらないタイプ」だったのではなかったか。
一九九〇年の早春。彼とあと二人、四人でバンコクで現地集合した。そこから鉄道で国境を越えマレーシアのペナン島を経由し、そこからバスでクアラルンプールへ移動し、さらにマレー半島中部にあるタマンネガラ国立公園(確か、タマンネガラというマレー語が国立公園という名だったはず)へボートで移動しそこで数日を過ごすという小さな旅をした。
その際に、旅慣れた彼と比べて、自分の英語でのコミュニケーション能力の幼児性に悔しい思いをしたことが今でも思い出される。正しく話そうと思うから、頭の中に文章を組み立ててからでないと言葉が出てこない。しかもボキャブラリーが足りないから、その文章すら自信がない。はたから見て、けっして上手というのではないものの、意志の疎通に苦労していないように見える彼が、ちょっと眩しかったのではなかったか。彼もぼくも、英語は劣等生(英語だけに限らないけれど)だったはずなんだけれどなぁ。
一九九〇年末、ぼくは青年海外協力隊に参加してケニアに旅立った。ぼくのケニア滞在中、彼はぼくの任地クウィセロ村までひとりでやってきた。その後、彼を首都のナイロビまで送って行ったのだったなぁ。楽しい思い出だ。
その彼が、パートナーを持ち、お子さんが生まれ……、その子はなんと我々と同じ高校に通い、大学も自宅から近い都内で……。その彼女が、海外に出かけた。そのことに彼がなんとなく安堵し、嬉しい気分であることは、ぼくにもよく理解できた。
外にでなければいけない、ということではけっしてない。けれども、外からでないと自分のことが見えにくいということは、確かにありそうだ。そのことによって自分が「変わるか」「変わらないか」はさておくとしても、“外”に出るというのはきっと素敵な体験だろう。特に若い世代ならば、なおさらだ。
そして、ひょんなことで、彼女の海外デビューの一部に、彼自身が同伴するということになったのだ。旅慣れた彼から見て、彼女の母語以外を使わざるを得ない場でのコミュニケーションはごくごく初心者のそれだったようだ。彼が語る彼女の様子は、まるでタイからマレーシアを旅した際のぼく自身のようだった。ひとつだけ違うのは、彼女が頼ろうとしたのが音声による自動翻訳機だったということ。たいした違いじゃない。
出会ってしまう。だから旅に出る。
さて、ぼくの東京往復。プノンペンから飛行機で移動したのは、今年二回目。四月にパリに行った際には、今回よりも旅先での移動は激しくなかったものの、ぼくはパリ滞在の後半に大きく体調を崩し、激しい血尿を起こした。そして、パリからブノンペンに戻った途端、高熱を出して夜中に救急車で搬送され、二週間の入院となったのだった。その際には、尿路感染に誘発された出血性胃潰瘍を起こし、敗血症を合併するという、まぁ書き様によってはなかなか際どい日々だったわけです。
今回の東京では、滞在中のスケジュールはパリでの日々よりもずっとタイトだった。けれども、途中体調を崩すことはなく、プノンペンに戻った後も平穏です。
“旅”するためには体調維持はどうしたって必要で、今回の東京旅は、パリ旅で壊しかけていた体調への信頼を少しだけ回復してくれたよう。自分で自分にちょっと一安心したのです。
なぜ“旅”に出たいのか? それはやっぱり出会いがあるから。それは人との出会いでもあるし(その多くが再会だとしても、それはやっぱり新たな出会いです)、人以外にも様々な出会いがある。インターネットを通じて以上に、それらの出会いのインパクトは強いのです。なぜだろう?でも、少なくともぼくには、それは確かなことらしい。
たとえば、帰路の機内で見た『ノー・アザー・ランド』というパレスチナのヨルダン川西岸地域のある村を舞台にしたドキュメンタリー映画との出会い。この映画は、米国でのアカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を今年三月に受賞しています。東京往復に利用したのは香港を基地とするキャセイ航空でした。復路ではこの映画が上映リストに入っていることには気づかず、ぼくはトム・クルーズ主演のミッシュンインポッシブルの最新作(かつ最終作?)を鑑賞したのでした。まぁ、面白かったけれど、それ以上でもそれ以下でもなかった。絶対安全確実娯楽大作映画が悪いってことはけしてないけれど、いくら見てもウンコにもならないってのは確かな気がする。けれども、『ノー・アザー・ランド』は腹にどーんと応えました。
パレスチナ全域で続いているイスラエルによる暴力については、この2年間(そして、それ以前からも)様々な媒体を通して知識と間接的体験を積み重ねてきという自覚がぼくにはある。ですから知識という点では、この映画から新たに得たことというのはあまりなかった。そこで語られる多くの“事実”は、すでに知識として学んだこと。けれども、映像を通じての疑似体験、あるいは目撃者になるということは、知識よりもより強烈に心身に響く。
その村は、イスラエル建国以前からそこにあるのだけれど、今やそこはイスラエル軍の演習地に指定され、村々の建物が順次強制的に破壊され、住民はそこを放棄することを迫れれている。それでも村の住民たちは、壊されたそばからあらたな住居を建設し、そしてそれがまた壊される。村は過去にその地形に自然造形された洞窟住居での生活という歴史を持っていて、住居を壊されれば、最後は祖先がくらしていたその洞窟が生活の場になる。世代を超えて、村人たちはその地にこだわる。『ノー・アザー・ランド』とは、もしぼくが和訳するならば『この地の他は無し』でしょうか。直訳すぎ? 『この地こそ』のほうが、いい?
映画での映像は、二年前のガザから抜け出たハマース勢力によるイスラエルへの大規模攻撃以前のもので、映画には描かれていないその後は「映画で撮られた日々以上に過酷になっている」とのこと。胸がきりきりと痛む。
その過酷になる以前の日々を描いた映画の終盤、その服装からイスラエル側入植者の民兵と思われる男が、暴力に丸腰で抗議する村人に圧倒され、思わず至近距離から村人の腹に向けてライフルを撃ってしまう場面が流れた。撃たれた男が腹を押さえて崩れ落ちる。ぼくはその時、思わず「アッ」と大きな声をあげてしまった。けして静かではない機内で、周りの乗客の何人かがぼくのほうを見るほどの大きな「アッ」。でも画面越しだから、血の匂いはしない。テロップで、撃たれた男性がその後亡くなったことが流れた。
撃った民兵のすぐわきには、イスラエル兵も機関銃を構えて立っていた。民兵が村人を撃った後も、その兵士が民兵を諫める様子もない。もちろん、民兵が現行犯で捕らえられるということもない。イスラエルが支配するパレスチナの地で、ごくごく普通のシーン。
これも旅に出たからこそ、出会えたこと。だとすれば、やはり旅は、ぼくにとって出なければいけないことなのです。出会いたい、のだ。見たい、のです。知らないですませたくない。でもそれ(知らないですませたくないこと)はあまりに多すぎて、ぼくにはとても取捨選択できない。あがいているけれども、どの「それ」と出会えるかはやっぱり縁次第。縁は拾いに行かなければ、手に入らない。


出会いだけが、ある。
初めて国境を超える旅にでた彼女は、何を見ただろうか? 何に出会ったろうか? それはぼくには希望だ。賭けのようなもの。たとえば、「日本はいいなぁ」かもしれない。それが悪いわけじゃない。ぼくもきっとそうだった。日本語は楽ちんさ。食事も、間違いなしさ。トイレのウォシュレットは彼女の世代ならもはや手放せないだろうし。何よりも、自分の枕、布団の匂い、お母さんの声、近所の風景、その唯一無二を知ること、それの体験があるから、その唯一無二を剥奪される人のことが少しだけ想像できるかもしれないわけで。
どこかで、「これって差別?」という瞬間があるとして、その結論が「差別する側に立ちたい」ってことだってあるだろう。何か嫌なことと出会ってしまい、「二度と来るか」、と思うのかもしれない。そんな経験の後に「差別される側の思いに至る」というのが期待される理想像なわけだけれど、でも人はそんなに解りやすくも単純でもない。
そういえば、タイからマレーシアを旅した友人のひとりは、そのぼくと旧友が主導を取った結果の安宿志向のバックパックスタイルに閉口して、「海外には、特に途上国には、二度と行きたくない」と旅の終わりに宣言したのだった。たとえそうだとしても、仕方がない。そう思えたのも、旅したからこそ。
外の世界を見て、他者との境界がぐっと低くなる人もいれば、「日本人ファースト」に拍車をかける人もいる。その感じようをコントロールすることはできない。もちろんぼくは、多くの人が前者であることを願っているけれど、その願いが届かないからといって嘆いても詮無いことだ。
だから、気になる。旧友の子が、旅から何を自分に持ち帰ったのか。でも、結論を急ぐことはないだろう。ゆっくり待つしかないのだから。正しい結論などが、そもそもないのだから。ただ、旅に出るからこその出会いがあり、その出会いが自らを俯瞰的にみる機会になる。それだけが確かなこと。
旧友がくれたSFの最後は次の文章で終わってた。
地上へと向かう穏やかな傾斜を上りながら、望は言った。
「うん、どこか遠くを見に行くよ」 (『一億年のテレスコープ』423ページ)
おっしゃ、俺もまだまだ見に行かなくちゃなぁ。














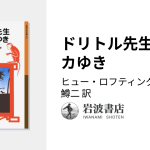
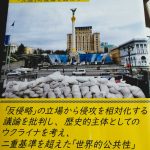

コメント、いただけたらとても嬉しいです