初めて出会ったのは上野国立科学博物館トイレ
テープワーム、a tapeworm、ワーム wormというのはハエの幼虫のようなウジ虫を指すことばで、それにテープ tape、ということばがくっついて、つまりは平べったいウジ虫、というイメージ。で、これは日本語にすると条虫、すなわちサナダムシの意味となる。サナダムシ、言葉としては知っていても、見たことはない人のほうが日本では多いのではないだろうか。
そのサナダムシと、ぼくはしばらく共存したことがあります。しかも、かなり長い間。4-5年は一緒にいたのではないだろうか。正確には、おそらく2匹(サナダムシを何匹と数えるかは、正確に考えるとなかなか難しい。後で出てくる「片節」ひとつひとつが成体と数えることも可能なので、2匹というのはあくまでイメージのようなものだ)。最初の一匹はやがて寿命がつき、その後、もう一度、違う個体がまた住みついた。もちろん、ぼくの小腸にだ。
感染地はカンボジア。感染源は、まず間違いなく牛肉だと思う。カンボジアの美味しい料理のひとつに、牛の半生肉、あるいは生肉をつかったサラダがあって、ぼくの好物のひとつ。その生牛肉にサナダムシの幼虫である嚢虫が潜んでいて、それがぼくの小腸で成虫となった。
こうして書いていると、つらつらと彼らとのいくつかのエピソードが思い出されるものだ。初めて自分の体内にサナダムシが存在していることを確認した日のこともよく覚えている。それは、たまたま帰国して子どもと出かけた上野の国立科学博物館の日本式水洗トイレでのことだった。洋式水洗トイレよりもより直際的にウンコが観察できる大便の中に、白くつやつやしたものが混在しているのに気がついたんだ。ぼくの第一印象は、「きれいだなぁ」だった。大便色のなかのみずみずしい白色が鮮やかだった。
もちろん、動揺もした。これは、どうしたものかとも思った。おそらく健康診断でぼくが“虫持ち”であることが判明し、薬を飲まなくてはならないのかなと覚悟した。
しかし、サナダムシは、ことさら厳しいと有名なODA実施機関の健康診断をなんなく乗り切った。特になんの指導もされなかったんだ。
翌年の健康診断で、ぼくは提出した大便のなかに、肛門からでてきたサナダムシの片節(一片)をあえて紛れ込ませた。ところが、そのときも何の指導もなかった。提出した大便は目視されることはなく、事務的に希釈されて、その希釈液の顕微鏡観察がされるだけなんだろうと想像する。サナダムシの卵は片節の中には大量に蓄えられているけれど、それはその片節が乾燥してはじめて外に飛び出してくる。だから、便の希釈液の顕微鏡検査では観察されないのだろう。
そんなわけで、その初代サナダムシは、ぼくの小腸内に2~3年滞在していた。

(画像は無料画像サイトから転用しております)。
サナダムシとの共生が始まる前に、ぼくは藤田紘一郎さんの寄生虫の関連本『笑うカイチュウ-寄生虫博士奮闘記』や、『空飛ぶ寄生虫』をすでに読んでいた。『笑うカイチュウ』は1994年の出版で、ベストセラー本だ。そこでは、寄生虫とヒトのアレルギーの関係や、サナダムシによるダイエットの話が興味深く書かれていた。
当時、メタボリックシンドローム予備軍の最前列に位置していたぼくにとって、特に痛みや下痢などの症状がなく、健康診断で引っかからない以上、ダイエットという言葉は魅力的だった。彼女(サナダムシは雌雄同体なので、彼女と呼ぶのはふさわしくないのかもしれないけれど)が、ぼくの体重増加をどれぐらい押し留めてくれていたかはわからない。サナダムシを飼っていたからといって、特に痩せるということもなかったように思う。彼女がいなかったら、もっと太っていたのかな??
というわけで、ぼくと彼女の共生が、片利共生(片方だけが利益を得る共生)だったのか、共利共生だったのかは、不確かなままだ。
あるとき、深酒をした翌朝、ぼくはひどい下痢をした。すると、下痢と一緒にダラ~ンという風情でサナダムシが長い状態で肛門から出てきたことがあった。びっくりしたけれど、この機会に先頭?まで引っ張り出そうと、割り箸で(トイレから割り箸を取りに行った状況は想像しないでください)、途中でちぎれないように慎重にくるくると巻き取ってみた。しかし、やはりあるところでプツンと切れてしまった。それでも、引き出した個体?は2メートルぐらいはあったろう。その物体は、勤務先の教員養成校でアルコール標本にした。もしかしたら今でも生物室の片隅に残っているかもしれない。
やがてその初代サナダムシは、気がついたときには消えてしまった。すこし残念な気もした。
二代目登場
そして1年ほど経ったころ、肛門がむずむずする懐かしい感覚があって、また片節が現れた。ただ、その片節は、どこがどうとは簡単には表現できないのだけれど、初代のものではないと、ぼくには断言できた。片節の長辺と短辺の長さのバランスが微妙に違うんだ。なるほど、サナダムシにも個性があるのだと改めて感じ入った。
2代目サナダムシは、カンボジアの仕事が終わって、次の勤務先のルワンダまで一緒だった。それでも、ルワンダ勤務が始まって2年近く経って起こった事故のときにはすでに消えていたように思う。事故後、下半身の感覚をなくすと、つまり便意もない。その詳細はまたの機会にするけれども、便意もないウンコを、今のぼくは指で直腸から掻き出している。だから、自分の便とは事故以前よりもずっと親しくつきあっている。だから自信を持っていえる。今、ぼくの小腸内に、サナダムシはいない。
でも、美味しい牛肉サラダをプノンペンで食すことはあるので、やがて三代目と出会う日がないとも限らない。次は、どんな奴だろう?
ちなみに、ヒトに寄生する条虫の中には、かなり悪さをするものもいるらしい。素人判断はやはり避けるべきで、もしあなたの便の中につやつやと活きのいい白い切片を見つけたら、きちんと医者にかかることをお勧めしておく。













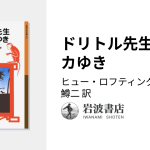
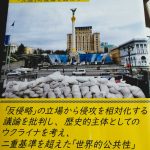

コメント、いただけたらとても嬉しいです