温泉大好き青年が、風呂嫌い親父に変貌するということ
熱いお湯に身体を浸す、「あー、気持ちいい」……。
はい、ぼくもそう思っていました。おそらく、いまでも入ってしまえば数分はそう思えると思います。とくに寒い季節のお風呂は気持ちいいですよね。
初めて長期に海外暮らしをして、もうすぐ帰国。日本に帰ったら何したい?
20代後半にケニアの田舎で2年間過ごしたとき、帰ったら「温泉行きたい!」と思っていました。実際に、帰国した冬に、信州のほうの温泉に行きました。降る雪を眺めながら入る露天風呂、はい、気持ちよかったです。
その後、フィリピンでくらして、カンボジアでくらして。住んだ場所は様々でしたけれど、なかには水を溜めて水浴びのみ、という場所もありました。シャワーはあってもお湯はでない環境も多かった。水浴び、暑い場所では、これがまた気持ちいいのです。
カンボジアの人たちは、朝昼夜と日に三回水浴びをする習慣があります。都会では、最近は変わりつつありますけれど、ぼくがプノンペンで働き出した2002年ごろ、公務員でも2~3時間昼休みをとるのが普通でした。多くの人は自宅に帰って昼食を摂っていました。さらに水浴びをして、服も着替えてという人が多かったのです。ぼくは昼の水浴びは習慣化しませんでしたけれど、朝起きて最初に水シャワー(あるいは、水浴び)は習慣になりました。夜も帰宅したら、最初にシャワー。
思い出してみると、フィリピン時代もそうでしたね。
そんな日々が長くなると、だんだんお湯を求める気持ちがなくなっていくのです。さらには、浸かることにも、執着しなくなってくる。日本に戻っても、温泉に行きたいという気持ちが、だんだん起きないようになってきたのです。むしろ、お湯に浸かると、疲れる感じがする。帰宅したらすぐにシャワーを浴びて、それからビールを飲む、という習慣がつくと、帰宅してお湯風呂に入るのはだんんだん面倒になるのです。早くビールが飲みたい!
ということで、気がつくと、ぼくは風呂入らずになっていました。風呂無しで、全然問題なーし。シャワーのみでOK。冬は流石にお湯が欲しいですけれど、夏は冷水のみでOK!日本にいても、そのまま。風呂桶にお湯を溜めることも、自分ですることはなくなりました。
温泉?疲れるから、あんまり行きたくなーい。そんなふうになってしまったのです。我ながら、その変貌ぶりに驚くのでした。
ミンダナオ島で出会った秘湯
フィリピンの最南部、ミンダナオ島のダバオで暮らしているとき。ミンダナオ島の東側、太平洋に面したバガンガ(Baganga)という小さい町の学校の視察に、休日もかねて出かけたことがありました。ミンダナオ島の太平洋に面した海岸には、大きな町がありません。ひとつの理由は、その太平洋海底は、一気に深い海溝につながっていて、ほとんど浅瀬がなく、良い漁場がないそうです。そのため、海に面しているのに、漁業が発達しなかったので大きな漁港もない。陸地側も広い平野はなく、ダバオ市南部に広がるようなバナナやパイナップルのプランテーションが発達することもありませんでした。
海岸沿いにくねくねとカーブの多い道(コンクリートの舗装道)をいけば、寒村がポツポツとならぶ、ちょっと寂しい風景が続きます。バガンガも小さな町でした。ところが、この町の近くに、立派な温泉があるのです。環太平洋地溝帯の一部であるフィリピン諸島には多くの火山がありますし、ときどき大きな地震も発生します。そんなところですから、ところどころに温泉もわく。
このバガンガにあった温泉が「立派」というのは、野外ですけれど風呂、というより小さなプールほどもあるコンクリート製の大きな風呂桶が作られていて、上流からわいたお湯がどんどんと掛け流れになっているのです。小さな川の一部で、川の水とお湯が混ざり合ってちょうどいい湯加減です。
地元の人が言うには、この温泉を最初に整備したのは、太平洋戦争時代にこの地に滞在した日本兵だということでした。
1941(昭和16)年12月、ハワイ真珠湾攻撃に象徴される太平洋戦争開戦時、ミンダナオ島のダバオには世界一大きな日本人居住区があり、その保護を名目に、真珠湾攻撃とほぼ同時にダバオにも日本軍が上陸し軍政がひかれます。そんなこともあって、おそらく1942(昭和17)年には、ミンダナオ島太平洋岸にも日本軍が点在していたのでしょう。
きっと、当初はかなりのんびりした駐屯になったんじゃないのかなぁ。それで、小さな川沿いに湧いていた温泉を見つけて、きっと日本兵は喜んだんでしょうねぇ。で、コンクリート製の大きな風呂が作らて、みんなで楽しんだのでしょう。なんか目に浮かぶようだなぁ。
その露天温泉プールは、今でもバガンガの人たちの遊び場になっているのです。ただ、真っ裸で浸かるのではなく、男性はパンツ着用、女性はさらにTシャツ着用のままで(ちゃんとした水着を持っている人は多くないのです)お湯につかります。
フィリピン時代、ぼくはまだ風呂嫌いということはありませんでしたから、バガンガに滞在した数日中、二度ほどその温泉を仲間たちと楽しみました。あの地まで足を伸ばして、あの温泉を楽しむというのは、ダバオの人たちにとってもごくごく稀なこと。まさに、地元の人たちだけが知る無名の秘湯でございました。きっと今でも、秘湯のままで残っているだろうなぁ。『行ってQ』でしたっけ?イモトアヤコさんが出られている、ぜひ彼女にあの秘湯ロケをおすすめしたいなぁ。絶対、いい内容になりますよ。
風呂文化の普及は難しいと思います。
こうして書いていると、たしかに温泉に対する熱狂的な嗜好って、かなり日本独特なものがありますよね。もちろん、世界には温泉を楽しむ文化はあちこちにありますけれど、でも、いまでも素っ裸で、公共風呂(あれも温泉の延長文化?)もまだ健在で、行く所行けば男女混浴もあってというジャパン、まさにディスカバリー(発見)。
大地溝帯としられる大陸移動進行中の場であるケニアにも湯が湧く場所はありました。けれど、地元の人たちがそれを整備して、風呂場にしているという話は聞いたことがありません。
大陸移動進行中の現場からは遠く離れ、当面大きな地震などはないだろうとされるカンボジアにも、お湯が湧いている場所があります。教員養成校の理科教官たちと、実地観察のツアーでそのお湯が沸く現場まで訪ねたことがあります。日本の温泉を数多く体験してきた者としては、はい、ものすごく貧弱なお湯湧く泉がありました。おそらく地下深い(圧力で火山がなくとも地温は上がります)ところで温められた地下水が、なんかの拍子で地上までつながっちゃったような場所なのでしょう。お湯湧く場所は沼地のようになっていて、その底からポコポコと小さな泡とともにお湯がわく。
ぼくらが視察にいった2003年ごろは、ただの沼地でしたけれど、その後、その場所を買った事業家がいて、ちょっとした遊び場?温泉場?にしたらしく、今では宿泊施設もできた、と聞いたことがあります。でも、その後も、日本人社会で話題になることもないので、温泉に対する厳しい日本人の目にかなった温泉場にはなっていないのだろうと思います。それに、カンボジアの人たちにとって温泉、それほど魅力があるものではないだろうしなぁ。
留学生らに風呂を無理強いすることなかれ
日本に海外からやってきて、たとえば留学生たちにとって、大きな関門、それも温泉、あるいはお風呂です。日本の友人知人につれられて温泉地を訪ねても、お風呂に入れない海外から客人たちはたくさんおられます。たとえ同性同士でも、他人の前で裸になることへの忌避感は、かなり世界共通です。むしろ日本のスッポンポン文化が稀。特に、ムスリムの人たちに、さらにはその中でも女性にとって、裸になってお風呂にはいる、しかも他の人も一緒に、というのは、もう想像もつかないようなハレンチなことでしょう。
日本では、ほとんどの風呂ではタオルをお湯につけるのも厳禁だったりしますよね。せめて大きなタオル、あるいは布を身体に巻いてお風呂に入ることが許されれば、かなり忌避感は少なくなると思うんですけれど。あるいはTシャツ着用OKとか。
裸のつきあい、なんて言葉がありますけれど、あれと同じ言い回し、どれぐらい世界にあるのだろう。(同様の意味のことばはあると思いますけれど、そこに「はだか」という言い回しがつかわれているかどうか?)きっとあんまりない表現だろうと思います。
障害者風呂?
ぼくが最後にお湯に身体を浸したのは、2015年1月のはずです。ルワンダで事故にあい、脊髄損傷で下半身完全麻痺になって、まだ病院時代。そのときの病院では、週に2回、お風呂に入れてくれたのです。風呂用ベッドの上で身体を洗った(洗ってくれた)後、そのベッドに横たわったまま、特設風呂に浸かることができたのでした。すでに風呂嫌いとなっていたぼくでしたけれど、寒い季節でしたし、「絶対入りたくない!」ってこともないので、遠慮なく楽しませてもらいました。だいたい入院生活、そうそう楽しいこともないわけで、風呂に入るのも新鮮でした。
その後移った病院では、ベッドのままシャワーが浴びれましたけれど、お風呂はなかった。そしてぼくはひとりで風呂場でシャワーを使う練習をつんで(トイレ使用も練習して)2015年7月末に入院生活を脱っしました。
滞在場所の風呂場の洗い場は車イスと同じ高さの「高床」にしてあって、シャワーを浴びる時は、車イスから高床に移乗して、そのまま床座りでシャワーを浴びます。湯船には浸かりませんから、お湯をためることも(ひとりならば)ありません。
カンボジアではトイレとシャワー室が一緒なので、便器(西洋風)で排便を済ませた後に、その便器に座ったままシャワーを浴びます。体幹が安定しないぼくにとって、便器に座ったまま石鹸を使ってシャワーを浴びるのは、そんなに簡単ではありません。滑って便器から床に落ちてしまうことがあるわけです。ですから、便器に座ったままでシャワーを浴びる場合は、家族の介助が必要です。(高床の場合は、介助なしでやってます)
最近は、風呂場で専用の車イスに乗り換えて、そのまま湯船に入ることができるという、障害者向けの温泉施設も少しずつ増えているようです。ただ、ぼくはそれに入りたいって、もう思わないんですよね。そうまでしてお湯に浸りたいという欲求がまったくありません。シャワーで十分。
ということで、もしかすると、多分、おそらく、もう一生、お湯に浸かる、つまりお風呂に入るということは、ぼくにはないかもしれません。怪我する前にお風呂嫌いになっておいて、ラッキーでした。もしお風呂好きのままでしたら、ねぇ。風呂に入りたーいという欲求があっても、それはなかなか大変だったわけで、怪我して落ち込むネタがひとつ増えていたわけですから。風呂嫌いになっておいて、ホントにラッキーであります。













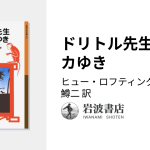
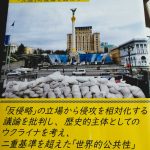

一時期温泉に凝った時期があって、九州の阿蘇山の麓の知る人ぞ知る温泉をはしごしたことがあります。岡山の露天風呂では、道路端に車が止まって暗い中、じっと露天風呂を見下ろしているところも見かけました。長期の海外出張から戻ると、自宅のお風呂で首まで浸かって、ナイロンタオルで全身の垢をこする、ごひいきの店でお好み焼き(広島風と言われるものが私のスタンダードなのであえて広島風とは言いたくないのですが)を食べるのがルーティンでした。刺身、寿司が死ぬほど好きというわけではないので、生魚はあまり恋しくないなぁ。もちろん、活きのいいおいしい魚は好きだけど。レストランではなくて、屋台のおいしいところに出張したい。