「それその怒りが地獄だ」
ある時、武士が訪ねてきて「地獄極楽はありますか」と尋ねた。白隠禅師は、武士に向かって「武士なのに地獄が怖いのかと」嘲笑った。武士は怒って、刀に手をかけた。白隠禅師は、「それその怒りが地獄だ」と諭した。(金森先生のカンボジア日記 (goo.ne.jp)2022年10月21日投稿から)
K先生のブログからのセンテンス。「それその怒りが地獄だ」。本当に怒る(いかる)、怒る(おこる)というのはなんとも疲れ果てる感情で、できれば無しですませたい、そう思います。40代のころ、数回、感情が爆発するような「怒り」に捉われたことがあります。その感情があまりにしんどくて、ある状況から私は無責任に逃げ出しました。
その際に、負担をかけることになっただろう人に対して申し訳ない気分は今でもあります。けれども、逃げ出したことは、ひとつの回答・選択肢として「仕方がなかった」と納得している気分もあります。怒りという、あんな絶対値の大きな負の感情を抱えて生きること、そしてそれを周りに吐き出すこと、それが継続する状況があったとき、そこから一刻も早く逃げ出すことはむしろ積極的に取るべき選択肢だったと思うのです。
逃げること、それを否定することはないだろうと。「それその怒りが地獄だ」という白陰禅氏の言葉、よくわかる気がするのです。だから地獄があるとして、逃げられるなら逃げた方がよいと。その逃げる先が、けして天国ではないことは解っているとして。それはそれで茨の道として、でも感情の爆発としての怒りに捉われているよりは、ましだ。
怒るのが当然でしょう? 世界が間違っているとしても
『怒りの哲学 正しい「怒り」は存在するか』(アグネス・カラード著 小川仁志監修 森山文那生訳 ニュートンプレス 2021)という本には、人種差別に対する「怒り」についての米国の哲学者アグネスカラードの考察と、それに対する様々な意見が書かれています。
まず、この世界では「怒り」は良くない感情と評価されてきた、という前提があります。「それその怒りが地獄だ」という白陰禅氏の言葉も、怒りを良くないモノとして語っていますよね。
けれども、世界が善くないとすれば、「怒り」はあって然るべきなのではないか、と著者は問うのです。怒りを、できれば避けるべきもの、うまくやり込めるべきもの(アンガーマネージメントなんて言葉もあるわけで)と捉える価値観のほうに、何か小賢しいものが潜んでいるのではないのかとアグネスカラードは私たちに問うのです。
そのたとえとして、米国での白人優越主義による人種差別の存在と、それに対する怒りが取り上げられています。つまり、個人さらには集団(黒人と呼ばれるアフリカ系の人たち)が理不尽な差別に晒されているという「世界の方が善くない」状況があるとすれば、当然それに晒されている人たちが怒りという感情を抱えるのは当然ではないか。そしてそんな怒りを抱える人たちを、怒りという負の感情の捉われた「良くない存在」と私たちの社会はマイナスに評価してきたのではないのかということです。「悪い世界で人は善い存在でいられるか」、注釈すれば「悪い世界で人は怒りという感情から距離を置いた善い存在でいられるか」ということをアグネスは問いかけるのです。彼女の答えは、「否、怒りはある!つまり、善い存在ではいられない!」なのです。「世界の方が善くない」から怒りを持つのであって、怒りを持つからといってその人たちを断罪するのは間違っているでしょう?とアグネスは訴えるのです。
つまり、怒りにもいろいろありそう、ということなのです。
40代のころに私が遭遇した私自身の怒りはどうだっただろうと思い返します。あれは、「世界の方が善くない」から生じた致し方のない感情だったろうか?
私の怒りは、特定の個人に向けられたものでした。その怒りを振り返ったとき、今私が気になっているのは、その人と私との関係は対等なものだったのだろうか……、ということです。確かに対等でありたい、という関係ではありました。けれども、「対等でありたい」という思いに、“正義”、あるいは“正しさ”はあっただろうか? 正直に言って、少々私の手に余る質問でもあります。たとえば、私とその人の関係の延長上の地平には、ジェンダー(社会的性差)がありました。それは、私とその人とのプライベートな関係ではコントロールできない歴史的で社会的な広がりを持った地平でした。そして、私はジェンダーの文脈ではどうしても強者《男》なのです。
「養ってやると言ってみろ!」とその人から叱責されたことがあります。そんな言葉、口が裂けても言うか!とそのとき私は思いました。それを言ったら、もう対等ではいられないじゃないかと、そのときの私は思ったのです。そして、私を責めた人との関係を呪いました。あるいは、軽蔑しました。失笑した。辛くもあった。そこに至るまで費やされた時間と行為、そのすべての選択とエネルギーが、恨めしかった。
それが積もりたまったものが、「怒り」となって私は叫び声を上げたのです。さて、あの「怒り」は「世界が善くないから」生まれた避けようがないものだったのだろうか? そうだ、ということはできないようにも思います。もっと小さな、個人的で、だから責任は私にある、つまらないもの、だったような気がします。とても恥ずかしくて、アグネスが世に問う「怒るのが当然でしょう?」という怒りと比べるなんてできない、と。
けれども。
私の個人的な「怒り」の及ばぬ領域にあるアグネスの言う人種差別への「怒り」を肯定する思いに共感する一方、でも「怒り」に正義を纏わせることに対する直感的な怖れも私にはあるのです。公憤、社会の悪に対して、個人の利害をこえて感じるいきどおり(コトバンクより)、というのだって、気をつけないと禄でもないものが多いんじゃないの?という危惧のようなものです。
つまり、公憤という正しい怒りと、個人の小さな怒りと、その間の境界線も曖昧模糊としているということです。だから、たとえ世界のほうが間違っているとしても、怒りには常に迷いが伴う。
マークボイルの語る怒り……も心に響きます
そして、アグネスの本に輪をかけて厄介なのが『モロトフ・カクテルをガンディと 平和主義者のための暴力論』(マーク・ボイル著 吉田奈緒子訳 ころから 2020)という前回の投稿でもちらりと紹介した過激なタイトルの本なのです。モロトフ・カクテルとは、火炎瓶のことで、もともとはロシアの侵攻に対抗したフィンランドで生まれた言葉だそうです。無抵抗平和主義者(村山注 本段落下の追記をぜひ)の権化ガンジーと火炎瓶というカクテルをご一緒しましょうという物騒なタイトルからして、読む前からため息が出てしまう厄介さではありませんか。カクテルのレシピ本によれば、モロトフという名のカクテルも実際に複数種あるのです。その中でも強烈なのは、「材料:ラム酒30ml、ウォッカ50ml、レモンシロップ30ml、レモンの輪」だそうで、ラム酒とウォッカを混ぜてしまうのですから、アルコールへの免疫のなさそうなあのガンジーさんであれば沈没は必須という感じです。
(追記*この段落中、ガンジーのことを「無抵抗平和主義者」と形容しました。Akiyo Takanoさんから、「無抵抗」というのはミスリードではないかというコメントをいただきました。はい、Akiyoさんの指摘にまったくもって同感です。ガンジーの「非暴力の不服従」行動は英国植民地主義に対する「抵抗」そのものでした。そしてその抵抗が力を持った。無抵抗平和主義という言葉は、Akiyoさんがご指摘のとおり、ミスリードになってしまいます。ごめんなさい!「無抵抗平和主義者の権化ガンジー」の箇所は「絶対平和主義非暴力主義の権化に祭り上げられたガンジー」と書き換えます。)
この厄介な本の中で、マークボイルは「非暴力じゃ、なんにも変わらないじゃないか!」と叫んでいます。世界が間違っているならば、その間違いを正すための行動が必要で、その行動すらを「暴力」として否定し排除する態度ではダメだろう、と彼は書くのです。大事なのは、それが効果的であること、それのみ、と。そして、私たちの社会は小さな暴力には敏感なくせに、企業と政府による生態系破壊といった大きな暴力には寛容だと、ボイルは書く。生態系破壊を止める直接行動を取らないのは、レイプ行為の現場を直面してしまったときに何もしないで立ち去るに等しいじゃないか。それなのに、この世界は生態系破壊を止めるための実力行為は暴力と評価判断している、最近はそれらもテロと呼んで。テロと評価判断しているのは、生態系破壊を進める企業と政府、さらには非暴力=善という思想に染まっている世間ですらも、です。
ボイル氏の主張は、私にはうなずける点が多々あります。ボイル氏が積極的な価値を見出そうとしている暴力も、公憤でしょう。ボイル氏がカバーする視点は、人間に限りません。全地球の生態系です。そして、その生態系破壊に対して意図的な反対行為を取れるのは、とりあえず人類だけなのです。だったら人間よ、ガンジー老よ、なぜ“銃”を取らないのか? 世間よ、ガンジー老よ、なぜモロトフカクテル(火炎瓶)を否定するのか? ボイル氏はアジるのです。ここでの銃は、もちろん比喩ですよ。
そして、ボイルは直接には「怒り」という言葉はつかっていませんが、“銃”を取り戦うという“暴力”という行為の背景にも当然怒りはあるでしょう。憤怒がある。そして尊厳です。
奴隷制にまつわる多くの物語が証明するように、人間の尊厳をもっとも奪うのは、自分自身の苦境ではなく、愛する人への攻撃を目にしながらなすすべを持たぬ状態である。(中略)そのような悲惨さから生じる無力感で尊厳をなくすのだとすれば、なすすべもなく手をこまねいているのをやめることで、うしなった尊厳をとりもどせるはずだ。(マークボイル前掲書 318~319ページ)
そして、ボイルにとって生態系破壊への攻撃は、愛する人への攻撃と地続きなのです。「大げさな」と彼を笑える人がいるとすれば、それはちょっと想像力の不足じゃないのと私は感じる。ボイルの思いにシンクロできるほどの強く生態系の危機を私は常日頃から意識しているわけではありません。のほほんと化石燃料を消費し、森林伐採の理由かもしれない果物や農作物を口にし、沖縄辺野古からのニュースをただ消費している。けれどもマークの思いはなんとなくわかる。きっとマークにシンクロできる領域を心に持っている人は少なくない。きっと、あの人なら、この人なら、あぁあの人も、私以上によっぽど彼の持つ自然愛?地球愛?にシンクロするのだろうとという顔が私には浮かぶのです。
公憤と私の間に横たわるのは、なんだろう?
なぜもっと怒らないのだ?なぜ、怒らずに黙っているのか?
何も抗議しないということは、「間違った世界」を肯定することだ。中立とは、常に多数の暴力を認める態度だ。暴力をふるうことと、それを見て見ぬふりをすることと(つまり直接暴力を振るってはいない)との間には、大きな差があるし、一方でほとんど差がない。
たとえば自己決定が侵害された。尊厳が侵されたことに憤慨する。侵された尊厳を回復するために暴力を使う(大声を上げるのも、今や暴力だ)。けれども、その怒りと暴力は、他者のシンクロを呼ぶことはめったにない。傍からは、それは単なる私怨私憤に見えてしまう。たとえその怒りの背景に、無数の同様の小さな怒りが存在しているとしても(たとえば、障害者が自らの自己決定にこだわるように)。
それに対して、集団同士の関係の中での尊厳の侵害と、それに対抗する正当防衛としての怒りと、さらにそこから派生する暴力がある。集団の怒りは、多くの場合“公憤”の装いをまとう。公憤は感染し拡大する。肥大した公憤による暴力の対象は不特定の多数に及ぶ。○○人なら、みんな敵だ!社会を正せ!
いや、だから抗議活動はあくまで平和的にしなければならない。暴力はいけない。それでは市民の共感は得られない。そういう考えを、非暴力神話、似非平和主義、エスカレートする非暴力志向と徹底的にたしなめたのが、火炎瓶とガンジーの例えだったのです。
公憤は大事だ。世界が間違っているなら、怒るべきだ。そして実力行使をしよう。…けれども人を殺めてはいけない?機械への暴力(たとえば辺野古を埋め立てる船やダンプカーを破壊する)はやるしかない。けれどけれど、正義の過程で事故が起こったら。そこで人を傷つけたら。大事の前の小事、犠牲はしょうがない?
マーク、ごめんよ。もうすぐ還暦で車イス者の僕は、たとえ似非平和主義と言われても、自らの身体を使って暴力行為には及べないよ。似非という批判は心して受け止める。そして、もしも機会があれば、似非の仮面を脱ぎ取れればいいと思う。つまり、並ばされた列から一歩前に出ることを、今から妄想し訓練するよ。もちろんそんな日がこないことを祈ってもいるけれど。でもね、祈るこの同じ日に、無意味に殺される人がいるのがこの世界なのも知っている。だから、僕に順番が回ってくることも覚悟しなくちゃと思う。
マーク、僕はね、人類はやがては絶滅すると思っている。人類だけが他の生命と違うはずはない。生態系の中で、他の生物が歩んできたように、繁栄と衰退と絶滅がある。マーク、君は言うだろう、ならば他の生物を道連れにするなと。そうだね。僕もそうは思う。
そんなふうに考えると、尊厳……、けっこう小さなことなのかもしれないよ。個々の尊厳なんて、実はちゃちなもんさ。もちろん、間違った世界はよくないよ。だから、君が書くように、それぞれできることをやろう。
けれどもね。それすらも、実は小さなことなのかもしれないよ。どうでもいいわけではなくてね。尊厳……、自己決定権……、うん、とても大事だよね。愛するものを守る。うん、守りたいね。でもね、僕はね、守れないことがあることを知っている。力足りなくて守れない。そしてね、それもありだと思っているんだよ。ごめんよ、まだうまく表現しきれてないな。まだ少しは残り時間があるから、また考えてみるよ。
おしまいに、最近の読書から「尊厳」そう来たかぁ! を3つご紹介
『狩りの思考法』角幡唯介著
狩りには動物との視点の一体化という側面があるのだが、そのせいか、狩りを前提に旅をすると、どうしても、自分も動物に殺される可能性を担保しておかなければならない、との摩訶不思議な義務感みたいな心情が生まれる。
もちろん、殺されたい、死にたい、などと思うわけではないのだが、でも、自分だけ死の危険のない安全な立場にたち、そこから動物を狩ることはゆるされないことなのではないか、人倫にもとることなのではないか、との感覚が心のどこかにある。
(中略)
このような感覚が生じるのは、動物の命には尊厳があり、狩りをおこなうにしてもその尊厳を踏みにじることは人倫に反する、との道徳律が、人間の心性に根源的に内在しているからだろう。動物の尊厳を保ちつつ、狩りをする。このアクロバティックな命題を解決するためには、ことによっては自分も死ぬ、あるいは殺される、との立場をのこしておかなければならない。相手が死ぬだけではなく、自分も死ぬ環境を確保しておくことではじめて双方の釣りあいはとれ、動物の尊厳を踏みにじらなくてすむからだ。(前掲書 アサヒグループホールディングス 2021 217~218ページ、文中の尊厳の強調は村山によるもの、以下の抜き書きでの尊厳も同じ)
狩りをする以上、自分も動物に殺される可能性を担保しておくことが、野生動物の尊厳を保つことになる。けして解りやすい考え方ではないかもしれません。角幡さんは“義務感”という言葉を使っていますが、それは責任という言葉にも置き換えることが可能です。
このような文章を読むと、どうしても星野道夫さんのことを思います。アラスカに魅せられて素敵な写真と文章を残してくれたあの写真家の星野さんです。彼はカムチャッカ半島で取材中に、ヒグマに襲われ食われました。彼は狩りをする人ではなかった。それでも、彼がこの角幡さんの文章を読めば、きっと共感するに違いないと私は妄想するのです。どんな気持ちで食われたのかな。もしそのときの気持ちを彼が綴ることができたなら、仕方がない、という表現があるんじゃないかと想像しています。
以前、このブログで災害時のペットと障害者との生命等々のことを書いたことがあります。そのこととも繋がっている角幡さんの文章です。おそらくこの繋がりの先には、原罪(けしてキリスト教や仏教などを背景とする必要のない言葉として使ったつもりです)とは何かという問いもあるような気がします。でも、それを今辿るのはやめましょう。(以下は、ペットのことを書いた以前のブログ投稿)
可愛らしいペットたちが怖くなることがある、障害のある私、というお話。 – 越境、ひっきりなし (incessant-crossingborder.com)
『狂気の時代 魔術・暴力・混沌のインドネシアをゆく』リチャード・ロイド・パリー著 濱野大道訳
サンパスにつながる道沿いで燃える家のそばで、黄色い鉢巻の少年が言った。「(中略)やつらが暴力を使うとき、ぼくらは自分たちの尊厳のために立ち上がることになる。だから、あいつらの家を焼くのです。ぼくたちはちゃんと心の復讐をする。あいつらには二度ともどってきてほしくないですね」(前掲書 みすず書房 2021 104ページ)
この本は1990年代後半のインドネシア政変の時代の貴重なレポートで、ボルネオ島(カリマンタン島)で起こった紛争についても書かれています。まだ20年ちょっと前に、百人千人単位で人が狩られ、首が切り落とされ、心臓や肝臓が喰われた。ショッキングですけれど、それはけして“蛮族”の仕業でもない。ボルネオの人たちが特殊ではない。このボルネオの事件の数年前には、ルワンダでももっと大規模に人狩りがあったのです。これらの行為と思想は、21世紀の現在にもつながっているというのが私の理解です。だから私の問題でもあります。私が首を落とされ、あるいは私がこの口を血に染める可能性がある。いや、本当に他人事ではない。意識するかどうかはさておき、世界は開いている、つながっているのですから。いつだって、黄色い鉢巻の彼は私だ。彼が狩った人たちも私だ。そのことから逃げることはできないのです。
この黄色い鉢巻の少年が使った“尊厳”は明らかに複数名詞・集合名詞を主語に語られています。そこから公憤までの距離はまったくありません。そのことにもはや驚きはない。でも私の心は、多分恐怖で、震えます。どうすりゃいいのよ。尊厳シリーズ、振り出しにもどる、って気分です。
気を取り直して……。一気に反転して、最後は気持ちのいいやつをご紹介します。
『ヘルシンキ生活の練習』朴沙羅著
(前略)私には娘が一人、息子が一人いると答えたら、アーダは、フィンランドで女性がいかに強く育てられるかについて熱く語ってくれた。
「OK、あなたの娘は強く育てられるでしょう。誰からもきちんと扱われるようにね。私たち女性は、すべてを手に入れたいのです。尊厳、お金、時間の余裕、安定した仕事、欲しい人は配偶者と家庭、それから買えるお値段の家もね。共に手に入れましょう!」(前掲書 筑摩書房 2021 24ページ)
カッコイイとは、こういうことさ。 ポルコ(ジブリ『紅の豚』)でとどまってたら、駄目なんじゃないかなぁ? 注 ここで注を書くのは野暮だとは思いつつ。「カッコイイとは、こういうことさ」というのはジブリ映画『紅の豚』のポスターにあったキャッチコピー、原案は糸井重里氏です。2年ほど前、尊敬する人はという私の問いに当時大学4年生の甥っ子は、ポルコ(『紅の豚』の主人公)、と答えました。やれやれ若いね、と思った私はこれを書いている段階で還暦まで1年半ほどでさぁ)
さて、これで尊厳シリーズはおしまい。ではでは、また。




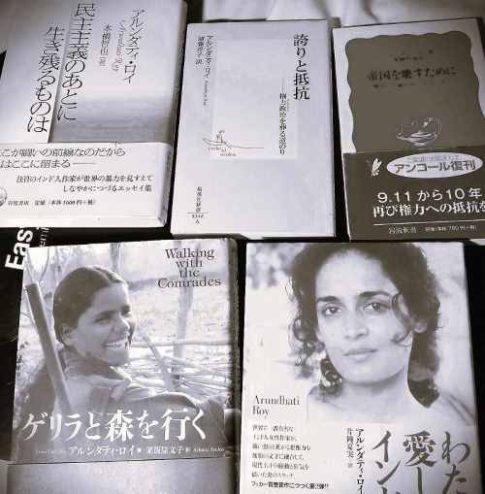






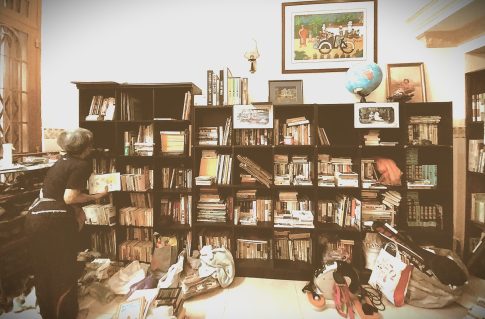

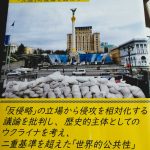

ガンジーの「非暴力不服従」について語る時「無抵抗」という言葉はミスリードでは?不服従はつまり抵抗するってことではないのかと。
Akiyo Takanoさん いつも読んでくれてありがとうございます。
さて、いただいたコメントは、本文中にある「無抵抗平和主義者の権化ガンジー」という箇所ですね。
なるほど、はい、まったくそのとおりでございます。ガンジーの行為はバリバリの「抵抗」でしたものね。ミスリード、まったくその通りです。完全に書き直してしまうと、私の恥が隠されてしまいますので、追記で対応します。
コメント、ありがとうございます!とっても嬉しい。
村山哲也