13世紀周達観が見たアンコールの胡椒と、19世紀後半の仏領インドシナ時代のカンポットの胡椒。その関係について、話はいよいよ佳境に入ります。カンポット胡椒を作ってきたのは海南系華人であるという20世紀ジャンデルヴェールの記述。さらに、18世紀にカンボジアタイ湾岸部で栄えた華人国家ハーティエンの存在。さて、そこから導き出せる結論とは?
(前回の投稿は以下でした)
ハーティエンという名の町は、カンボジアとベトナムとの国境から少しベトナム側に入ったところに今もある。ハーティエンから東さらに南東側に広がるのがメコン川の三角州、メコンデルタだ。このメコンデルタを含む現在のベトナム南部は、フランス領時代はコーチシナと呼ばれていて、多くのカンボジアの人たちにとっては「ベトナムに盗られてしまった」地域と認識されている。もともとはベトナム北部に始まったベトナム(阮朝)が南下し、17世期末にはその勢力をメコンデルタまで伸ばしてきた。そして18世紀初頭には、それまでカンボジア住民が多数派だったメコンデルタを併合してしまう。ベトナム南部に位置する大都市ホーチミン市(旧サイゴン)を、カンボジアの人たちは17世紀までの名前であるプレイノコールと呼んで、「あそこはカンボジアの領地だった」と今でも悔しそうにする。
18世紀から19世紀なかごろまでのカンボジアタイ湾沿岸部をめぐる歴史 ハーティエン小国、さらにベトナムとタイの強い干渉

国境の東側はカンボジアのカンポット県になる。
そのコーチシナ支配がカンボジアからベトナムへと移り変わる時代に、現在のハーティエン周辺に中国からの移民たちによる独立国家があった。
カンボジア王朝年代記が語る歴史の中では、この華人系独立国家があったことは無視されている。高校で歴史を教えていたカンボジア教員に聞いてみたところ、カンボジアの現在の歴史教科書も、この華人国家にはまったく触れていない。つまり、カンボジア正史の中からは消えてしまった幻の独立国ハーティエンということになる。(ということで、ハーティエンを独立国だったと書いたら、カンボジアでは不敬罪に問われてしまう可能性があったりするんじゃないかと、少し心配しながら書きます。)
『海から見た歴史』という本は、17世紀から18世紀にかけての南シナ海沿岸の様子を以下のように書いている。
かくして、華人の移住の拡大にともない、南シナ海沿海各地ではチャイナタウンが激増した。現地での華人社会は、政治権力に依拠しない、自前の地縁・血縁のネットワークによってなりたっていた。チャイナタウンのなかには、タイ湾の沿岸地域のように、ソンクラーの呉氏やハーティエンの鄭(ばく)氏など、華人主導の港市として成長して半独立政権に発展したものもあった。[i]
ソンクラーというのは、現在のタイのマレーシア国境近く、タイ湾に面したマレー半島東側にある県の名前である。このソンクラー県の東隣にあるパッターニ県はトメピレス「東方諸国記」で胡椒生産地として記載された場所だ。ソンクラーを18世紀後半から支配した呉氏は現在の福建省から移民してきた華人で、その支配は19世紀いっぱい続いた。
ハーティエンに関しては、北川香子が書いた二つの資料、『岩波講座 東南アジア史4 東南アジア近世国家群の展開―18世紀』[ii]中の「ハーティエン」の項と、さらに『カンボジア史再考』[iii]とに、詳しい記述がある。それを要約すると次のようになる。
ハーティエンの支配者となった鄭玖は一六五五年広東省の生まれで、一六七一年にプノンペンに渡り、国王に寵愛され、一六八六年前後にハーティエンの商業を統括する立場となった。そのころハーティエンはタイ東岸の港のひとつとして姿を現し始めていた。しかしカンボジア王権のタイ湾岸の海港への関心は低かった。
ハーティエンからはメコン川支流であるバサック川はさらなる支流によって結ばれ、陸路でもウドンと連絡していた。十八世紀初頭のハーティエンは、西方海上からカンボジアに向かう入り口であった。鄭玖はハーティエンにおいて、賭博場の開設と賭博税の徴収、銀山開発、流民の招集と七社村の建設を行っている。七社村にはコンポート(カンポット)とスライアンバル(スラエオンバル)も含まれる。一七一一年、メコン川三角州に勢力を広げつつあったベトナム阮朝からも承認を受け、鄭玖はカンボジアとベトナムとの二重の官位を得た。当時カンボジアはシャム(タイ)とベトナムを巻き込んだ戦争の最中であり、ハーティエンもシャム水軍の攻撃を受けて一度は廃墟となり、そのとき鄭玖はスライアンバルに避難している。
一七三五年に鄭玖は死に、子の鄭天賜が後を継いだ。鄭天賜は、一七四二年に日本の徳川幕府にクメール語(カンボジア語)の書簡を送り、その中でカンボジア王を自称している。さらに、カンボジア国内の内紛に乗じ鄭天賜はカンボジア王の義父となり、タイ湾沿岸を含むカンボジア南部で大きな権力を持つに至った。
一七六七年、タイのアユタヤ王朝がビルマ軍によって滅ぼされた際、アユタヤの王子たちがハーティエンの鄭天賜を頼って亡命している。その後、ハーティエン勢力はタイ湾東部の支配を巡ってタイ湾地域の潮州系華人と対立する。そして、トンブリーに新たな王朝を建てた潮州系のタークシン王によって一七七一年に攻められ、ハーティエン華人国家は消滅した。鄭天賜も捕虜として捕らえられて一七八〇年にトンブリーで自死した。[iv]
ハーティエンの鄭氏勢力が崩壊後、カンボジア王家の正史である『王朝年代記』に、始めてコムポート(カンポット)という地名が現れる[v]。しかし、鄭氏のハーティエン国が消滅後、カンボジアのタイ湾沿岸部は、タイとベトナムが直接勢力を争う場となり、18世紀後半から19前半に至る半世紀ほどは、カンボジアの主権がタイ湾沿岸におよぶことはなかった。
19世紀中ごろの1845年に、ベトナムとタイの和平が成立すると、ようやく海岸部はカンボジアの支配下におかれ、前述(連載の前回)したようにアンドゥオン王によるカンポット港の整備が始まる。その結果、カムポットはカンボジア唯一の国際港となるけれど、その役割は短かった。1863年にカンボジアが仏領インドシナに含まれると、カンボジアの輸出品はメコン川を下りサイゴンに運ばれるようになり、カンポット港はさびれていく。カンポットの国際港としての歴史は、ほんの20年弱に過ぎない。
フランス植民地政府による『コンポート地誌』[vi]によれば、19世紀のハーティエンは、その背後で栽培される胡椒のサイゴンへの積出港だった。胡椒栽培の労働力は、海南島からジャンクで運ばれ、カンポット近郊のケップの港に上陸した海南系華人だった。『コムポート地誌』が編纂された20世紀初頭には、ハーティエン背後の胡椒栽培はすでに下火で、胡椒栽培は西へ移動し、カンポット周辺で盛んになったという。連作障害による病気の発生などが、胡椒の作地が移動したことが、ハーティエンでの胡椒栽培が下火になった背景にあった。
ジャンデルヴェールは胡椒栽培が1840年ごろ導入されたと書いた。1840年ごろというのは、タイ湾沿岸でのベトナムとタイの勢力争いの最期の数年にあたる。
紛争中に、タイの潮州系華人が胡椒を現在のカンボジア湾岸沿いに持ち込み、海南系華人を労働力として使ったのだろうか。しかし、紛争中、あるいは紛争が再発する可能性がある中で、華人が胡椒農園に投資し整備するのはかなりのリスクが伴うように思える。胡椒は、支柱等の初期投資が必要で、しかも収穫まで5年かかるのだ。その後も長期に収穫が続かなければ、初期投資を回収できないことになる。
カンポット胡椒は華人ネットワークによって導入された。
その時期は、早ければ18世紀中ごろ(ハーティエン小国の最盛期)、あるいは18世紀後半(タークシン王に守られた潮州勢力)、遅くとも19世紀前半のベトナムとタイとの紛争小康期だ。
ひとつの仮説は、潮州系華人のタイ王タークシンがハーティエン小国を滅ぼした後、潮州人が入植し、胡椒栽培を始め、海南系華人を労働力として動員した。タークシンがハーティエンを滅ぼしたのは1771年だから、それ以降、つまり18世紀後半に胡椒栽培が始まったと考えることができる。
あるいは、胡椒栽培導入はこの1840年以前にベトナムとタイの紛争が小康状態を保ったときに行われたのかもしれない。とすれば、19世紀初頭か。
さらには、もっとさかのぼって、ハーティエン小国がもっとも栄えたと思われる鄭天賜の時代、18世紀中頃にその起源がある可能性も否定できない。なんといってもハーティエン国は華人の国だった。タイ湾対岸のマレー半島東岸部では17世紀後半には華人による胡椒栽培が始まっていたのだから、華人国家のハーティエン小国が18世紀中頃までに胡椒の栽培に着手していたとしても、驚くにはあたらないだろう。そうであったとしても、ハーティエン小国の消滅と、その後のベトナムとタイとの紛争によって、胡椒栽培が大規模化することはなかった。
そして、19世紀中頃、1840年あたりに胡椒栽培がハーティエン周辺のタイ湾岸部で再開された。さらに、胡椒の大輸出地だったスマトラ島西部のアチェ王国が、オランダの侵略を受けたアチェ戦争によって衰退するという好機を得て、カンボジアのタイ湾岸部での胡椒栽培は、仏領時代に大きく栄えた。
文献が限られる中で、以上の仮設は、かなり妥当性のある筋書きではないだろうか。
13世紀に周達観が見たアンコールの胡椒は、その後も細々とメコン川流域内陸部で続いていたかもしれない。しかし、20世紀のカンポットで栽培され「世界一」と呼ばれた胡椒の起源は、早ければ18世紀半ば、遅くとも19世紀半ばまでに、マレー半島東岸、あるいはタイ湾西側(現在のタイ領海岸部)のどこかから、華人ネットワークのよって導入され(導入した資本力は海南系によるものではなく)、労働力として海南系華人が育てた胡椒にあったのだろう。
一方、カンボジアの胡椒の独自性を示す証言もある。
カンボジアで胡椒の栽培と販売に従事する匿名の日本人専門家は、カンボジアの胡椒の葉は卵型で、(マレーシアの一部を除いた)東南アジアの一般的な胡椒の木(ハート型の葉を持つ)とはかなり違うことを教えてくれた。世界のあちこちで胡椒の木を見ている専門家には、カンボジアの胡椒の木には葉の形をはじめ、幾つかの特異性があるように思えるという。カンボジア特有の卵型の葉をもつ胡椒の木は、13世紀に周達観が見たアンコールでの胡椒が、中世以降もカンボジアで細々と育てられていたものを起源にするのではないかと、その専門家は考える。そして、他の場所で胡椒栽培を学んだ華人が、カンボジアに移住した後、このカンボジア特有の胡椒の木を集約的な方法で栽培するようになったのではないかと、その専門家は言う。
気になるのは、マレーシアの一部の地域にも卵型の葉を持つ胡椒があることだ。それがカンボジアの卵型の葉をもつ胡椒と同じ系列のものであれば、私(筆者)の「ハーティエン小国時代、あるいはそれ以降にに、マレー半島のどこかから華人ネットワークが胡椒をもたらした」という仮説を強力に後押しすることになる。しかし、もしかしたら、マレーシアの一部で育てられている卵型の葉を持つ胡椒が、華人ネットワークを通じてカンボジアから持ち込まれた可能性もあるわけで、その真相解明は簡単ではない。
DNA調査などを駆使することで、今後、胡椒の越境の歴史の詳細が明らかになっていくことを楽しみにしたい。
[i] 262ページ 羽田正編 小島毅監修『東アジア海域に漕ぎだす1 海から見た歴史』東京大学出版会 2013
[ii] 池端雪浦・他/編『岩波講座 東南アジア史4 東南アジア近世国家群の展開―18世紀』岩波書店 2001
[iii] 北川香子/著 『カンボジア史再考』連合出版 2006
[iv] 189~209ページ 北川香子/著 「7.ハーティエン」池端雪浦・他/編『岩波講座 東南アジア史4 東南アジア近世国家群の展開―18世紀』、 さらには157~164ページ 北川香子/著 『カンボジア史再考』
[v] 162ページ 北川香子/著 『カンボジア史再考』
[vi] Rousseau,A., Monotraphie de la residence de Kampot et de la cote cambodgiennne du golfe de Sia, Saigon, 1918, 204ページ 北川香子/著 「7.ハーティエン」池端雪浦・他/編『岩波講座 東南アジア史4 東南アジア近世国家群の展開―18世紀』



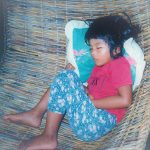









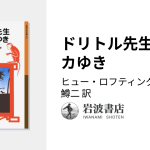
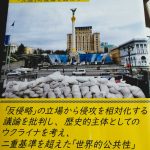

本当に克明な物語にワクワクします!