ロビンウィリアムス、死んじゃったんですよねぇ
米国の俳優、ロビンウィリアムス。2014年に亡くなってしまった。63歳。ロビンウィリアムスは、ぼくの好きな俳優さんのひとりだった。
1987『グッドモーニング, ベトナム(Good Morning, Vietnam)』、1989『いまを生きる(Dead Poets Society)』、1990『レナードの朝(Awakenings)』、1997『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち(Good Will Hunting)』、1998『パッチ・アダムス トゥルー・ストーリー(Patch Adams)』……、とぼくの好きなロビンウィリアムの映画を並べてみると、ほぼ10年ちょっとの間で公開されているものばかりだ。彼が30代から40代、つまり最も油が乗っているころの映画なんだろう。それぞれの映画をどんな状況で最初に見たのかはほとんど覚えていないのだけれど、『いまを生きる』だけは、覚えている。1990年末に青年海外協力隊に参加してケニアに理数科教員として赴任する前に、銀座の映画館で見たのが最初だ。当時、ぼくは20代なかば。
映画の中でロビンウィリアムスが演じる熱血教師を、そのまま全肯定するのが当時のぼくだった。
映画の冒頭、全寮制名門高校の文学(国語?)の授業で、ロビン演じる新任教師キーティングは普通に教科書冒頭の「詩を説明する文章」を生徒に読ませた後、「じゃ、そのくだらないことが書いてあるページを破り捨てろ!」と指示する。つまり、「詩とはなにか」なんて説明は、無意味どころか、詩を感じる感性に対する冒涜である、というわけだ。
当然戸惑う生徒たち。
けれど、厳格な寮制高校の伝統を重んじる教育に「抑圧」されていた生徒たちは、教室の教壇の上に登り立って教室を見渡すことで視点の相違を体感させたり、文学の授業なのに校庭でサッカーボールを蹴っ飛ばして思い浮かぶ単語を叫ばせるという、キーティングの型破りな授業に魅入られていく。
えーと、ストーリーを紹介するのがこのブログの役割ではないので、すっ飛ばすと、とにかく自由に羽ばたこうとする若者たちと、規制しようとする親や学校の対立があり、結果、その板挟みに苦しんだ青年がひとり、自死するに至る。もちろん、キーティングは自分の理想がもたらした悲劇に悩むし、結局、その責任を取らされて学校を去る。
けれども、映画のラストシーン、教室を去るキーティングに対して、残された生徒たち(全員ではない)は、校長の厳しい制止にもかかわらず、キーティングの「教え」に対する精一杯の敬意を表す(知らない人もいるでしょうから、ここはネタバレしないように、自重して書きませんね、機会があれば、この映画と出会っちゃってくださいませ)。このラストシーンに、ぼくは心震えたわけです。
新しい価値観の導入に際して
この感動的なラストをもたらした、キーティングの教育哲学に、今もぼくは異論はありません。教育とは、人が自由な心を獲得し、個人として自立する手助けをするためのもの。それがキーティングが生徒たちに実践しようとしたこと。
「詩とはなにか?」を散文でだらだらと説明するなんて、阿呆くさいこと。詩とは感じるもの、どうしようもなく生まれてしまうもの。国語教師であったキーティングにとって、それを生徒たちに体感させることが、彼の理想とする教育の実践だったわけだ。
中学や高校で教科書を「破け!」と指示する国語教師と出逢えば、ぼくだって憧れちゃっただろう。もちろん、そのことが友人の自死につながってしまったとしても、それは「事故」だっただろう。事故は、起こってしまうことが、ある。
ただ、もしぼくがケニアで働いたクウィセロ中等学校でキーティングを気取って「教科書を破け!」と生徒に熱く語ったら、どうだっただろう。幸い?ぼくが大学で取得した教員免許は高校理科で、クウィセロで教えたのも、科学や数学だった。2次方程式の解法を公式なんかで覚えるのは数学に対する冒涜だ!あれは暗記するものじゃないよ、自分で勝手に導き出すものだ……とか、空気抵抗を無視するなんて、それは生活からの乖離で単なる頭でっかちの机上の空論だ……とか、そういう「原理主義(?)」にぼくが陥ることはなかった。でも、国語教師だったら?社会教師だったら?
ふふふふふ、それはそれで楽しかったかなぁ。
まぁ、教科書を破れはあまりにも極端としても、たとえば昨日のブログでふれた、「教師が生徒に知識を伝達する」という旧来の教育から、「教師は生徒の主体的な学びを支援する、ファシリテーターに過ぎない」(2000年中ごろにカンボジアで実施されたユニセフ主催の研修で、若い“白人系”指導者がカンボジアの現職教員に通訳つきで語るのを、ぼく自身が目撃しています)という新しい教育法への移行だって、それはときには「型破り」でもある。
ぼくが目撃した上記の研修で、カンボジアの現職教員たちは、「生徒自身が学ぶ」という意味を、「先生は答えを教えてはいけない」と受け止め、その結果、大混乱を起こした。たとえば、その研修で実施された小学校算数の模擬授業では、ある課題に生徒たちがグループワークを通して明らかに間違った回答にたどり着いてしまったとき、けれど先生はその過ちを指摘しなかった。なぜなら、それは生徒たち自身が“主体的に”たどりついた尊い結果であったからだ(と、その先生は新しい教育手法を理解し、実践したんだ)。
教員として学校で教えた経験を持っていなかったユネスコの若い指導者も、これまでの「教え方」にダメ出しをだされた現職教員も、「理想」という曲のリズムにあわせて無理やりダンスを踊っているような感じを、ぼくは受けた。(ぼくは、その研修をたまたま見学させてもらった立場だったので、研修内容に口出しすることははばかられたんだ。だから、とにかく、黙って“観察”していた。)
そこでの「型破り」とキーティングの「型破り」な実践との大きな違いは、キーティングがひとりの新米教師だったのに対し、ユニセフが国際的に大きな力を持つ権力者だった、ということだ。名門学校という組織の中では、新米教師の「型破り」に対して、校長やPTAは断固従来の指導法を擁護した。けれど、カンボジアの教育界で校長にあたる教育大臣たちが、ユニセフの「型破り」に抗議するということは、なかったはずだ。
書いてみたら、なんか“大人”っぽくて、呆れちゃうけれど
今、『いまを生きる』や、これまで見てきた途上国での教育の質改善の取り組みや、を思い出して思うのは、改革にはそれが効果を発揮できる環境整備が欠かせないよなぁってことだ。そして、学校教育という営みは、学校という場単独で成立するものではなくて、学校をふくめたもっと大きな場としての社会と無関係ではいられない、ってこと。
たとえば、こんな思考実験はどうだろう。非民主的な社会があったとして、そこに素晴らしく民主的な教育を実践する私立学校を、海外の篤志家が建設し運営する。篤志家が目指すのは、その学校の卒業生が、まだ非民主的なその社会の変革のリーダーになることだ。
けれど、その学校を卒業後、卒業生たちはかなり孤立無援だ。卒業生たちが学んだ理想は、その社会では通用しないことばかりだ。進学した大学で、あるいは職場で、教授や上司の意見に異を唱えれば、それは生意気と受け取られてしまう。教育の場とその後に生きる社会との間にあまりに大きな乖離があれば、結局、苦労するのは「理想とされた教育の場」ですごした未来の大人たちだったりしないか?
もちろん、これはあくまで思考実験で、現実はもっともっと複雑だ。おそらく、現代の多くの社会は、民主的な面もあれば、非民主的な面もある。上意下達だって、すべてがすべて否定されるものではないだろうし、また新しい声すべてが排除されるってことでもない。そもそも、篤志家が目指した民主的な「理想の教育」が、本当にその学校で実践されるのかだってわからない。「理想の教育」があるとして、その完全な実践なんか、ないだろう。そもそも、理想の教育? 理想の民主主義?
と書きつつも、まぁ、“大人”っぽいことを文章にしていることよ、と思う。結局、世の中、「折衷」って言っているわけですものね。まぁまぁ、斟酌、ほどほど、無理せず、……。
いや、でもやっぱりそういうことは無視すればいいってもんじゃない、って特に国際開発なんてことの末端で、さらに支援する側で、やってきた者としては、やはり思うんです。だって、そりゃ、迷惑だと思うもん、小さな権力者(支援する側)が介入するって。口出しのない支援(資金)が、歓迎されるのも、それを歓迎する支援される側に立てば、その気持ちはわかるところもあります。
でも、口出しなしとすれば、資金で貢献できない「ぼく」は、もう手を引くしかない。口出しするなら、どうやってそれがうまく伝わり活かされるかを、やっぱり考える。それが、たとえ、昔は否定していた“大人の技法”に近づいていってしまうとしても。
だからさ、キーティング、やっぱり君のやり方は、性急すぎたのよ、と思う。教科書を破ったのは良かったけれど、もっと理解者を増やさなければ、破綻は遅かれ早かれだったと。理想に殉じるとか、やっぱりダメだと。
ロビンウィリアムスならば、こんな表情を見せるしかない、って場面でしょうか?
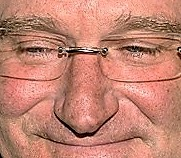
俳優ロビンウィリアムスの全盛期を体感できて、よかった
『レナードの朝』で、ロバートデニーロ演じる一時的に薬で覚醒した患者が、しかし薬の効果は持続せず、さらに強い副作用にも悩まされたとき、「どうしてぼくを起こしたんだ」と非難するとき、その言葉をうけた医師(ロビン)が見せる、悲しみと困惑の中で浮かべる表情。あの表情は、ロビンでしか表現できないものだったと、ぼくは思います。だから、ロビンウィリアムス演じる役を見てしまうと、もうあの役はロビンでしか演じえない、と思う。
ぼくも、もはや残された道は、あの表情かなぁ。理想をぶつぶつ言いつつ、でも「ほどほど」ってことも付け加えてしまう以上、もうあの表情を浮かべて逃げるしかないかなぁ。うん、それもひとつの手かもしれません。
とにかく、ロビンウィリアムスがいてくれてよかったと、ぼくは本当に思います。映画を離れたロビンは、どうやら悩み多い人だったようで、後年は鬱や病気に悩まされ、その死も“自死”だったように聞きます。でも、一ファンとしては、それをここでは触れるのはやめましょう。
そして、さて、ロビンのあの表情を手に入れるには、どうしたらいいかなぁ。それはそれで、なかなか簡単ではなさそうです。
そして思い出すべきなのは、ロビンの真骨頂は、コメディ、笑いにあったのも確か。ここでは紹介していませんけれど、彼のコメディを全面に出した映画もけっこうあります。だから、あの哀愁を手に入れるには、笑いもすっごく大事なんだよね。笑いがあるから、あの哀愁もある。そうか、せめて、まずは、もっと笑わなくちゃなぁと、このコロナ禍の日々で思ったりしています。
ではでは、今日はこの辺で。

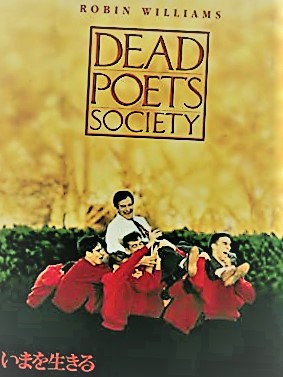












コメント、いただけたらとても嬉しいです