11月29日、12月7日(以下から飛べます)と書き継いできた、カンボジアの車イス者ボッパーさんの話。今回はその第3回、そしてひとまず一区切りです。
PPCIL Phnom Penh Center for Independent Living
(プノンペン自立生活センター)
前回の投稿で、ボッパーさんが職業訓練校で知り合った仲間を通して、PPCIL(プノンペン自立生活センター)に加わったことを書いた。PPCIL設立者であるサミスさんは、ボッパーさんが訓練校のデレビ/ラジオ修理コースで学んだときに、コース指導官の助手を務めていた。ボッパーさんが卒業後、自宅でテレビ/ラジオ修理の店を開いたときも、2度ほどアドバイスに訪ねてくれたこともあったそうだ。

サミスさんが日本でダスキンによる「アジア太平洋障害者リーダー育成事業」に参加し、カンボジアにもどり、障害を持つ仲間たちに声をかけPPCILを設立しようとしたとき、そのスタッフの中に女性がいなかった。男性だけでPPCILを運営していくことが、ジェンダーの視点からよろしくないことを、誰かがしっかりと認識していたのだろう。女性のスタッフが必要だということで、地元でくすぶっていたボッパーさんに声がかかり、24歳の彼女は、再びプノンペンに向かった。
ボッパーさんも含めて6名のメンバーで始まったPPCILは、最初スタッフの給与も賄えなかった。サミスさんが「ビデオ機のリージョンコード機能を外す仕事」で貯めたお金を持ち出しして、なんとかスタッフは生活した。プノンペンに家のないスタッフは事務所に雑魚寝した。
「事務所には冷蔵庫もなかった。ガスもないから、炭火を使って調理して、みんなで食べました。携帯電話も最初は事務所にひとつしかなくて、それをみんなでシェアしてたんです」
「サラリーが低くて、それが一番の問題でした。家族がいて、生計を安定させなければいけなくて、PPCILを続けていけないスタッフもいました。でも、共同生活はとっても面白かった」
ボッパーさんは、職業訓練校で感じた自由を、ようやく取り戻したんだ。
PPCILにとって、海外からの支援者、つまりスポンサーを探すことは至上命題だった。そして、サミスさんが日本での研修で培ったネットワークが、そのとき役に立った。日本から定期的にサポートしてくれる人たちが見つかった。やがて、スタッフにも給与が支払われるようになった。
「最初のサラリーは90ドルでした」
やがてボッパーさんはレンタルハウスを借りてひとりで生活を始める。彼女の自立生活そのものが、初期のPPCILのプロジェクトだった。
障害者は家族の庇護の元、家に閉じこもりで、社会と交流もなく過ごすのが当たり前だったカンボジアで、車イスで、しかも女性がひとりで生活することを“証明”するのがボッパーさんの“役割”だった。あ
日本でも、1970年代以降、それまで施設に半分強制収容のように閉じ込められていた脳性麻痺者や脊髄損傷者といった障害者が、社会に出て生活する手段を切り開いてきた歴史がある。そのときも障害者自らが、身のまわりの人たちを巻き込みながらまず実践し、それを後追いするようにして徐々に公的な福祉制度が整えられていった。
さらに遡れば、日本の障害者自立運動に大きな影響を与えたのは、1960年代に米国で始まった障害者たちの自立活動だった。
つまり、PPCILとボッパーさんがやったことも、障害者自身がまず最初に実践する、ということだった。もちろんその論理的背景は、サミスさんが「アジア太平洋障害者リーダー育成事業」で学んできたことにある。米国から日本に渡されたバトンが、カンボジアにも継ったわけだ。
ダスキン アジア太平洋障害者リーダー育成事業
ダスキンが「国連・アジア太平洋障害者の十年(1993~2002)」事業推進の一環として「アジア太平洋障害者リーダー育成事業https://www.normanet.ne.jp/~duskin/」を開始したのは1999年。この事業は、もともとは米国企業のミスタードーナッツが始めた社会事業にその根っこがあるようだ。(ダスキンのこの事業への支援の歴史については、以下のページに詳しい。財団概要:歴史│ダスキン愛の輪基金 (ainowa.jp)https://www.normanet.ne.jp/~duskin/)
サミスさんは、2006年に日本での研修に参加し、そこで障害者自立の思想と実践を学んだ。そして2009年にPPCILを開いた。そして、PPCILからサミスさんに続いて、アジア太平洋障害者リーダー育成事業に参加したのがボッパーさんだった。
10ヶ月の研修を終えて、最後に日本語で書いたボッパーさんの最終報告書、そこで書かれた「新しい人になりました」「私はできます」という力強い文章を先の12月9日の投稿で紹介した。
研修参加以前は、自分に自信が持てず、サミスさんに指示されたことだけをこなすことに汲々としていたボッパーさんだったけれど、新しい人になり、自分でできると研修の最後に宣言したように、カンボジアにもどって活き活きと活動し始める。
「日本でのプログラムはとてもハードだったから、カンボジアに帰ってきて1ヶ月ぐらいは休んでのんびりしたかったんです。でも、やる気満々だったから、1週間だけ休んで、すぐにPPCILの仕事に出てきました」
PPCIL設立時のメンバーで、現在もPPCILで活動しているのはサミスさんとボッパーさんのふたりだけだ。スタッフが辞めていった最大の理由は、やはり収入だった。ただ、これはぼくの想像だけれど、直接に障害者自立の思想に触れたかどうかが、PPCILでの活動を続けていくには重要だったんじゃないだろうか。日本での10ヶ月の研修は、参加者の価値観に革命を起こすだけの中身の濃いものなのだろうと思う。その研修に参加する機会を得られなかったメンバーが、離脱していったのは仕方がないことだったのかもしれない。
とにかく、PPCILの10年ちょっとの歴史の中で、知らず知らずのうちに、ボッパーさんは組織のリーダー格となっていった。
ボッパーさんは今ではプロジェクトマネージャーとして、PPCILによる活動を運営する立場にある。計画を立て、スタッフを組織し、指示を出す。彼女は、その仕事にとてもやりがいを感じている。
「私の背中はまっすぐじゃなくて、車イスに座っていても、ときどきひどく背中が痛むことがあるんです。そんなときはベッドに横になります。でも、ベッドの上でも働きます」
恋をしたことはあるけれど、内緒です
リーダー格となったボッパーさんにも悩みはある。
「私は、他人からは、厳しいとか、はっきりモノをいう人、って見られることが多いです。だからカンボジアの男性が私に恋に落ちるのは、なかなか大変なんだろうと思います。カンボジアの文化では、強い女の人は結婚相手の対象にはなかなかならないから。」
「子ども?今のサラリーでは、自分のことだけで精一杯だから。将来の生活にも、経済的に不安があるし。それでも、子ども、欲しい気持ちもあるなぁ。今34才なので、40才までそんなチャンスがあれば、欲しいです。けれど、今は彼氏はいないから」
「以前、私に恋しちゃった男性もいますよ。でも、その人はお酒のみで、仕事も不安定だったから、私は彼のことがそんなに好きじゃなくて、ちょっと面倒くさかった。その人?他の人と結婚しちゃいましたよ」
「私のほうが恋におちたこと? もちろんありますよ! でも、その話は内緒、秘密です。障害があると、消極的になっちゃうところは、私にもあります」
前回紹介した、研修最終報告書には以下の文章もあった。
「自分の障害が、とても恥ずかしくて嫌いでした。私は家族にとって「問題」だとも思っていました。毎晩いろいろなことをたくさん考えて、悲しくなって、泣きました」
そんな10代の日々、ボッパーさんも自殺を考えたことがあった。でも仏教の戒律では、自殺は罪だ。それにボッパーさんは心のどこかに、かすかな希望を持っていたとも語る。
今、ボッパーさんが目指すのは「もっと勉強して、事業の報告書を英語で自分で書けるようになる」ことだという。海外の支援者への報告書書きはサミスさん頼みという状況を、彼女は変えたいんだ。会計報告書も自分で書けるようになりたい。そしていつの日が障害者が自由に旅して寝泊まりできるようなホテルをプノンペンに建てたい。
まだまだ先は長い。そんな彼女の未来を“目撃する人”に、ぼくはなれたらいいなぁと思っている。













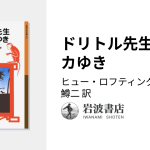
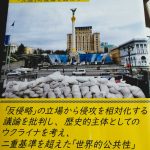

前回の記事をいわき市にある医療創成大学の原田真之介へ転送したところ、「記事の方、ありがとうございます。今後やるインタビュー研究にとって非常に参考なります。」とのお返事でした。
お知り合いの方に広めていただき、ありがとうございます! 村山哲也