「素」を、「そ」と読むか、「す」と読むか。前回の投稿では、素に「そ」と送り仮名を振りました。けれども、辞書をあれこれ漁ってみたところ、素が単独で表記されるときには、「す」と読むほうが一般的みたいですね。
【素(す):ありのまま、純粋、無垢、手を加えない】
私が「素」を思うとき、思い浮かべるのは最首星子さんのことです。星子さんのことは、以前、このブログでも書いたことがあります。
星子さんのこと – 越境、ひっきりなし (incessant-crossingborder.com)
星子さんの「素」→ チーム星子
彼女は重度のダウン症を持って生まれ、知的障害、視覚障害などの重複障害があり、言葉もしゃべれない。1976年8月生まれの彼女は『星子が居る』出版当時は20歳を迎えた頃でしたけれど、現在では40代半ばで、はい、お元気です。以下に紹介する記事は3年前のものでちょい古いけれど、今年4月にも他の記事でも星子さんの健在が知れるのでした。(以下は有料記事ですけれど、前半は無料で公開されているので、それだけでも星子さんの消息はちらりとわかるよ)
「人あっての社会」障害の娘から学んだ 元全共闘の教授:朝日新聞デジタル (asahi.com)
本を読んだ限りの浅い理解ではありますけれど、想像するに、星子さんもあれやこれやで“飾る”ことがある。父親で『星子が居る』の著者である悟さんの前と、岩盤のような母子関係を築いてきた母親の五十鈴さんの前とでは、違う顔を見せるのですから。
それでも、星子さんの“飾り”は質素だろうと思う。多くの人が身と心にまとうだろうデコレーションと比べれば、ずっとあっさりしていて、つまり星子さんの日々は彼女の素にいつも近いモノだろうと想像するのです。
それと比較すると、自分を振り返っても、いやいやデコレーションにいつも忙しいわけです。そして、その装飾は、やっぱりどこか「かっこつけ」だし「はったり」に思える。つまり、必要のない、無ければ無いで済む、そんなもの。
いや、化粧にしても、それはそれであっていいし、場合によっては、「あったほうがいい」こともあるだろうとは思います。けれども、それはあんまり厚くなくていいんじゃないだろうか(いや、厚化粧好きでも問題はなくて、まさに他人の化粧に口出しするのはまったくもって余計なお世話!!)。「かっこつけ」も「はったり」も、まぁ薄めにいきましょうや、と思う自分がいるのです。
そう思う自分を振り返ると、やはり年齢の積み重ねは、「かっこつけ」や「はったり」を薄くする効果はあったように感じています。デコレーションはあんまりなくてよい。そしてそれが心地よい。
さらには、素でいけたほうが、楽なわけです。素で立つ。そう覚悟してしまえば、あとの判断はあちら(自分の外)に任せちゃえばいい。そこはもう、自分ではコントロールできない領域なのです。お気に召さなければ、それはそれ、まぁ仕方がない。
すべての場面で受け入れられる、そんなの無理じゃーん、と思えばいい。蓼食う虫も好き好き、なんですから。まぁ、たまには「蓼」も好きって言ってもらえることもあるんじゃないかと。
(ところで、蓼食う虫も好き好き、と読むと、なんかグーッと意味が反転していきますよね。まったくもって濁音、油断ならず、であります)
とにかく、そんな感じで、私の場合はできれば薄化粧で、素で立てればと思う。そんなことを思うと、星子さんの素っ気なさが、私のスタンダードになっていくような気がするのです。目指すのは、彼女ではないか、と。
星子さんが私に教えてくれたのは、「ただ存在することを何人も否定できない」ということだったように思います(正確には、父親である最首悟さんの文章を通しての学びですから、教えてくれたのは悟氏なのかもしれないけれど、その悟氏だって星子さんから多々学んで書いているわけですから、やっぱり星子さんが教えてくれているのだと思うのです)。そして「ただ存在する」「ただ生きている」の「ただ」の部分が、実はかなり貴重で素敵で鍵なのです(ここで、意味深い、とか、価値がある、とかいう「意味論」や「価値論」に結びついていく言葉を使っちゃダメと思うので、なかなか表現するためのボキャブラリーが難しいのですけれど)。つまり。ただ存在していることから発せられるメッセージを読み取れる人がいる。
「ただ存在している」の「ただ」に語感の悪さを感じるとすれば、「そっと存在している」「静かに存在している」「ひっそり存在している」という言葉がうまくはまるでしょうか。
そっと存在し、ひっそり生きている星子さんには、(私に、チームむらやまてつや、があるように)やはりチーム星子のメンバーが生じています。そして、チーム星子の人々は、星子さんの存在を慈しむことができる。実際に、愛しく慈しんでいるのです。そこに至るになにか特別な“飾り”は必要ないということを、星子さんは示してくれている。
開発業界の「はったり」と、「やれることを、やる」という割り切りと → 障害の受容へ
たしかに、星子さんと私とでは、在り様がきっといろいろと違う。生き様も、もちろん違う。同じように独りで音楽を楽しんでいたとして、その同じ行為が他者にとって星子さんの場合は慈しみの対象で、私の場合なら怠惰なだけ、ということはあり得る。それは星子さんと私がちょっと違うから仕方がない。そのことは、別に、不平等でも不公平でもない。
だから、星子さんができないことをできる(らしい)私は、まぁ一応、そのできる(らしい)ことをする。ただ、だからといって私が偉いわけでもない。そして、私よりもたくさん「できることをしている」人たちも万といるわけですし。そして、彼らが私より偉いわけでもやっぱりない、のだ。
私が食い扶持を得ていた「国際開発支援」という業界は、他の業界にも増して強烈な学歴社会です(まずそのヒエラルキーのトップに君臨する国連系・国際開発銀行系が、超激学歴社会であることがそれを象徴しています)。そんな世界では、ある種の虚勢を張るみたいなことが日常茶飯事にあったように思います。下世話なネタでいえば、履歴書に書き込む語学の能力みたいな欄。英語が筆頭に書いてあって、A(よくできる)、B(ほぼほぼできる)、C(ややできる)、みたいな選択肢が用意されていて、それを自分で選ぶ。そして、そこは当然Aを選べということになるわけです。実際はBやCでも、ここは虚勢を張ってでもA、みたいな。もちろん、現実としては当然各種英語検定試験の結果(しかも数年以内のもの)を添付することが求められたりするわけのですから、いくら自己評価で虚勢を張っても、検定試験結果の“客観的”な数値が“事実”は語ってしまうわけです。それでも、心意気としては、Aを選べみたいな風潮があったりした(今もあるのかなぁ?)
そういう虚勢、はったりは、まぁ許されるような“空気”があるように私は感じていました。むしろ、「はったりぐらいかませて一人前」というような価値観。そしてきっとその空気の中で、私も虚勢で装備し、自分を実際のよりも大きく見せようとしていた日もあったのです。
そういう無駄?な飾りが、だんだん取れてきたと実感をもって感じられるようになったのは、40代後半になってからだったんじゃないかなぁ。「やれることを、やる」ということは、「やれないことは、やれない」ということです、当然です。そして、とにかく「やれることを、やる」ということを大事にしようと本気で思い行動するようになってきたなぁ、みたいにふと思ったりしていたのです。「やれることを、やる」のも、やっぱりそれなりに大変で、だから虚勢を張る暇などない!ということでもあったように、今振り返ると感じます。
おそらく、そういう心境がちらちらと生まれていたことは、50歳で下半身完全麻痺という障害を得た際に、その障害を受容することを比較的容易にしたのでしょう。だって、「やれることを、やる」だけだよなぁ、ってことですから。それは、車イス者になっても同じこと。
そして、確かに前よりも「やれること」は狭まったのですけれど、まぁ、そういう素になったということですから、仕方ないって風に思えたのです。
そんな格好悪い自分も、素の自分なのだから
そして、障害を得た後の、リハビリテーションのベッドの上で『星子が居る』を読んだのです。あぁ、星子さんは私だ、と思ったのですよね。彼女と私と、どこが違うのだ?と。同じじゃないか、と。
素になってしまえば、みんなそれほど差があるわけじゃない。それが素直に認められたような気がしたのです。
障害者9歳の私としては、今後ますます装飾を脱ぎ捨てて素で生きたいなぁと思ったりしているのです。
実際には、まだまだかっこつけをしている自分がいるし、またそのことでじくじくと思い悩んだりもする。自分のかっこ悪さに辟易とするわけです。でもまぁ、そんな格好悪い自分も、素の自分なのだから。その程度のもんだから、まぁ仕方ないじゃん?ってことなわけですわ。
若い人が素になれないのは、当然だろうなぁなんて思ったりもする。少なくとも私はそうでした。飾りを落とせるようになったのは、ようやく40代後半ですから。それだって、まだまだなわけで。虚勢を張る元気もあっていいよ、とは若い人に言ってもいいかな。でも自分を飾り過ぎて、素の自分がわからなくならないように、気をつけてね、ですね。













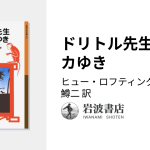
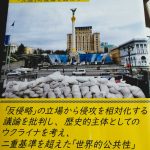

コメント、いただけたらとても嬉しいです