多くの翻訳を手がけ詩人でもある管啓次郎は『トロピカル・ゴシップ 混血地帯の旅と思考』という本の中で、パパイヤを食べるか否かが「違い」として抽出され、そこに差別が生まれる事象がブラジル北東部にあることを紹介している。
食べるものがちがえば、私とかれらはまったくちがう人間。これは外見でただちにわかる身体的特徴の差異に匹敵するほどの、あきらかな差異化だ。ブラジル北東海岸ベルナンブゴ州の水の都レシーフィの住民たちは、すぐ近くの町オリンダの住民たちを「パパ・ママンぅ」(パパイヤ食い)と呼んで、自分たちから切断した。ほとばしる美しさの丘の町オリンダに対するこの呼び名の影には、ブラジル植民地経営の先発国であるポルトガル(オリンダを創設した)に対する、レシーフィを拠点とした十七世紀オランダの闘争心がこめられていた。
氾濫するパパイヤがありふれた、何の値打ちもないものであれば「パパイヤ食い」は嘲笑の対象となる。あるいは逆に「パパイヤ食い」をおとしめ蔑む必要があるからこそ、パパイヤが負の価値を担うべきものとして選びだされる。負の徴をおびるのは、パパイヤが先か、「パパイヤ食い」が先か。おそらくこのメカニズムは、どちらが先というものではなく、同時にレシーフィの住民の心にめばえるのだろう。自分は他人とはちがう(そして優越しているのは自分だ)という差異をめぐる戦いが、人間の世界の究極の謎なき謎であるなら。私を造形する食物が、すでに動かし難く与件となった身体的当口調〈肌や眼や髪の色、骨格、顔つき〉につぐ戦いの場として浮上してくるのはもっともだ。[i]
ありふれた食べ物でさえ境界となりえ、さらにそれが差別に繋がる。そんな人間のやっかいな感情を、管は「人間の世界の究極の謎なき謎」と表現している。管が究極と呼ぶように、人の、あるいは社会の、「違い」に対する執着は根深い。この十七世紀オランダのポルトガルに対する敵対心は、もちろん二十一世紀オリンダの住民からすれば、偏屈で迷惑なレッテル張りでしかないはずだ。
だいたい人は、どうやって自分は確実に「〇〇人」であると断定できるのだろう。ぼくには国籍以外、自分を日本人と意識するのは、日本語を母語としていることぐらいしか思いつかない。自分の祖先にアイヌがいるか、渡来人がいるか、知りようがない。
言語と国家の関係を研究してきた言語学者の田中克彦は、自分の著作の中で「日本人」と「日本語人」を併用しながら、できれば一貫して「日本語人」を使いたいと書いている[ii]。田中は、日本語共同体に参加できる人、つまり日本語を使いこなす人を「日本語人」という一つの社会の構成単位と考えようと提唱することで、「日本人」の曖昧模糊さを突いた。田中によれば、日本人という言葉は、人種、文化、国家への所属、民族を含むという。日本人は「人種」でもあるのか[iii]。しかし、それはまったくつまらない、どうでもいいことのようにぼくには思える。
ぼくは、米国人小説家のポールオースターが書く自分の「出自」をめぐる文章に強い共感を覚える。文中の「君」は、オースター自身のことを指している。
自分がどこから来たのかはまったくわからないのだから、君はもうずっと前に、僕は東半球のあらゆる人種の複合物であって、アフリカアラブ中国インドコーカサスが混じった、一個の肉体の中で無数の文明が相対立するるつぼなのだ、と想定することに決めた。これは何よりもまず倫理上の選択である。人種という、君に言わせれば偽物でしかない問題を除去する方便である。そんな問題に拘泥するのは自分を貶めることにしかならない。ゆえに君は、自覚的に、あらゆる人間であることに決めた。最大限に、この上なく自由に自分であるためには、自分の中のすべての人間を抱擁することに決めた。君が誰であるかは神秘であり、その神秘が解決される望みは決してないのだから。[iv]
ぼくがまだボランティアでケニアにいたころのこと。乗り合わせたバスが道端で待っていた遊牧民を乗せた。すると同乗する乗客はその遊牧民をあからさまに見下す態度をとった。そっとわけを聞けば「(遊牧民たちは)肌の色が黒い」と言う。そういう乗客らも、ぼくからみればあきらかに濃い肌の色をし、つまり「黒人」なのだ。確かにその遊牧民は、乗客が着る町の服装とはひと目みれば違いのわかる遊牧民としての衣装をし、肌もより漆黒だ。それが蔑みの対象となるのが、当時のぼくには驚きだった。
「肌の色が黒い」のが蔑みの対象となるならば、あなたたちと、あなたたちよりも肌の色があきらかに「白っぽい」私との関係性はどうなるのか。私は「肌の色」を理由に、あなたたちを差別できるのか。「黒は美しい」とあなたたちの「仲間」が北アメリカで拳を突き上げてきたことを知らないのか。正直にいえば、ぼくは遊牧民を嘲笑う彼等に対して、優越感を持った。私(たち)のほうがより開明し開化している存在として。
でも、このような「究極の謎なき謎」である不愉快な境界は、日本社会に限っても、今日も再生産を繰り返している。あのとき遊牧民を嘲笑った彼等を、今のぼくは簡単に隣人に見つけることがある。自分が「◯◯人」であることに拘泥し自らを貶めるように見える人たちが、身近な社会にもたくさんいることを認めないわけにはいかない。でも、それは日本人として恥ずかしい、とはぼくはもう思わない。「日本人」としてそう思うことは、もうすでに帰属の罠にはまることだとも思うから。
ぼくは日本人だと思う。日本のパスポートを使っているから、なんて理由でなく、日本に生まれ、日本に育ち、日本語で育ったぼくは、胸を張ってぼくは日本人だと言う権利があると思う。でも、日本に生まれなかったら、もう日本人にはなれないのかな?日本で育たなかったら、日本人にはなれないのかな?日本語が不自由だったら日本人にはなれないのかな?日本に生まれ、日本で育ち、日本語で育っても、別に日本人でなくてもいいのかな?………あなたはナニ人?ぼくはこのあとも死ぬまで日本人でもいいのかな?日本人でいられるのかな?
[i] 206~207ページ 管啓次郎/著『トロピカル・ゴシップ(混血地帯の旅と思考)』青土社1998
[ii]171ページ 田中克彦/著『クレオール語と日本語』岩波書店1999
[iii] 176ページ 田中克彦/著『クレオール語と日本語』岩波書店1999
[iv] 106ページ ポール・オースター/著 柴田元幸/訳 『冬の日誌』新潮社 2017




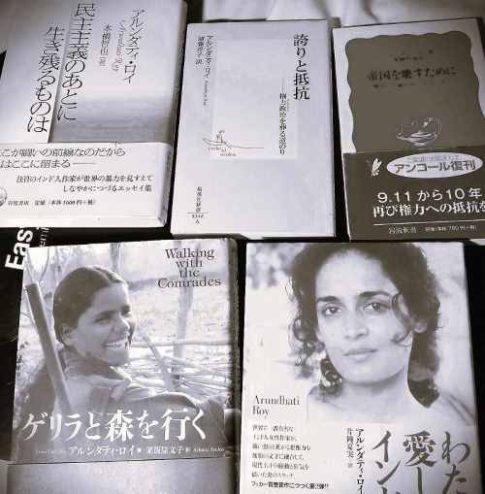








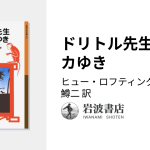
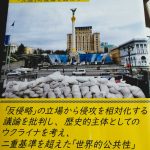

コメント、いただけたらとても嬉しいです